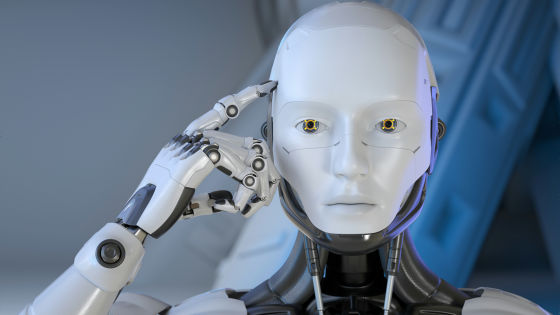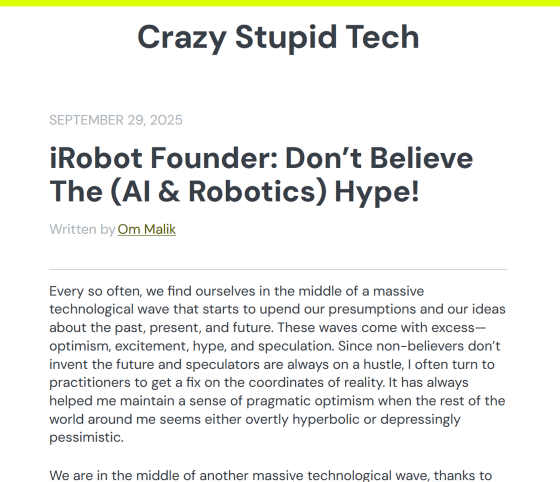近年はAIやロボット工学といった分野に膨大な資金がつぎ込まれ、多種多様なプロモーション活動が行われていますが、「実際のところAIやロボットで何ができるようになるのか?」がよくわからないという人もいるはず。そんな中、テクノロジーライターのオム・マリク氏が、MITコンピュータ科学・人工知能研究所で教授を務め、お掃除ロボット「ルンバ」を生み出したiRobotの創業者でもあるロドニー・ブルックス氏と、ロボット工学やAIについて対談した内容を公開しました。
iRobot Founder: Don’t Believe The (AI & Robotics) Hype! – Crazy Stupid Tech
https://crazystupidtech.com/2025/09/29/irobot-founder-dont-believe-the-ai-robotics-hype/
◆人々は「Machine Idiots(機械バカ)」になっているのか?
近年はテクノロジーの発達に伴って生活や仕事の効率が向上したと考える人が多くいますが、マリク氏は人々が盲目的に機械に従っているだけであり、「機械バカ」になっているのではないかと主張します。実際、マリク氏はWaymoの自動運転車に乗った際、地図上では正しい場所を指し示していたにもかかわらず、実際にはまったく違う場所で降ろされたことがあったそうです。
これに対しブルックス氏は、「今朝Uberでここに来た時、運転手に今どこの通りにいるのかを尋ねましたが、『ただそれ(GPS)に従っているだけです』と言って、まったく場所をわかっていませんでした。そこが問題なんです。人間の介入があるにもかかわらず、何か問題が起きた時にどうすればいいのか本人にもまったくわかっていないのです」と述べています。
ブルックス氏が現在経営しているRobust.AIという企業では、配送倉庫に導入する「スマートカート」の開発に取り組んでいます。記事作成時点では多くの倉庫従業員がピッキング作業に従事していますが、目的の商品を拾い上げるために倉庫の中を歩き回ったり、重い荷物を持ち上げたり、荷物を載せたカートを動かしたりする作業は体に多くの負担をかけます。
Robust.AIが開発する「Carta」というスマートカートは自分の現在位置を把握し、ピッキング対象の商品がある位置まで従業員を誘導し、音声制御で自走して積載した商品を所定の場所まで運びます。また、従業員はCartaを手動で制御することも可能だそうで、小さな画面や文字ベースのソフトウェアを持ち運ぶ既存のソリューションと比べ、従業員がコントロールする能力を維持しつつ負担を減らせるとのこと。ブルックス氏は、「私の会社は常に人間がコントロールできるようにしてきました」と述べ、ルンバが動かなくなっても人間が持ち上げて移動させられるように、Cartaも人間が操作できるようにしていると説明しました。
また、Cartaは人間が通路をふさいでいる時は移動するまで待ち、動かないパレットでふさがれている時は方向転換し、中央システムに障害物の存在を知らせるというシンプルなシステムを採用しています。これについてブルックス氏は、「これはシンプルなインテリジェンスであり、今日私たちが実現し、信頼性の高いものにできるものです。派手なものではありません。作業員の作業を楽にし、効率を高めるためのテクノロジーなのです」と述べました。
by Robust.AI
◆「ヒューマノイドロボット」という概念がもたらす弊害とは?
マリク氏とブルックス氏の会話はヒューマノイドロボットに関するものに移行し、マリク氏が「ロボットやロボット工学については誤解があります。最大の誤解は、ロボットが人間の形をしていると考えることです」「私たちは、ロボットと言われて『広告を絶え間なく配信するシステム』を思い浮かべることはありません。これもロボットなのですが」と述べました。
これに対しブルックス氏は、「物理的なロボットについて私がいつも言っているのは、その外見が何をできるのかを約束するということです。ルンバは床に置かれた小さな円盤であり、大した約束はしませんでした。見た人は『窓掃除なんかできないだろう』と思うでしょうが、床掃除をする姿は想像できます。しかし人間の形をしていたら、人間ができることは何でもできると約束しているかのようです。だからこそヒューマノイドロボットは人々にとって魅力的に見えるのです。それは驚くべき約束を売り込んでいるのです」と指摘。ヒューマノイドロボットはその外見から、「人間ができることなら何でもできる」かのような期待を抱かせていると主張しています。
◆ロボット工学の現状と問題とは?
ブルックス氏はアメリカのロボット工学の現状について、大量の計算リソースによる処理能力の向上や小型センサーの発展は良いニュースだと主張。また、ブルックス氏の会社ではここ数年で普及した電動スクーターのハブモーターをロボットに使用することで、安価かつ大量に部品を手に入れられるようになったそうです。
ロボットに関連するさまざまなテクノロジーが進歩した一方で、人々は「自然環境のロングテール」を過小評価しがちだとのこと。たとえはブルックス氏が初めて自動運転車に関する講演会に出席したのは1979年のことで、1990年には自動運転車がパリ市内を走り、2007年には国防高等研究計画局(DARPA)が開発した自動運転車がお披露目されました。しかし、記事作成時点でも自動運転車が展開されているのは一部地域にとどまり、その普及は非常にゆっくりとしたスピードになっています。こうした技術の普及を妨げるさまざまな要因を、ブルックス氏は「自然環境のロングテール」と呼んでいます。
ブルックス氏は、「企業などは派手なデモンストレーションに走る傾向がありますが、こうしたデモンストレーションは現実環境に対応していません。テクノロジーは混沌(こんとん)とした現実の中で機能しなければなりません。だからこそ、これらの技術の実現には長い時間がかかるのです」と述べました。
◆イノベーションや世界に対するアプローチを再考する必要があるのか?
マリク氏はブルックス氏に対し、「これまでの知識を踏まえて、私たちはイノベーションや教育への取り組み方、そして世界観そのものを再考するべきだと考えますか?『ネットワーク以前』の時代は40年もうまく機能していましたが、今や私たちは新たな強度とリズムを持つ『ネットワーク以後』の世界に生きているのです」と問いかけました。
この問いにブルックス氏は、「世界には新しいリズムが生まれつつありますが、私が恐れるのは皆が『新しい正統派』に飛びつくことです。ここ数年、ニューラルネットワークベースのAIに取り組んでいない人は時代遅れで、恐竜同然だと言われ続けています。しかし、長年研究されてきた非ニューラルネットワークベースの技術が、今後重要性を増すことは間違いないだろうと断言できます」と答えています。
ブルックス氏は、普遍的な言語処理マシンを搭載している生成AIは、「言語を理解する」ということの意味に疑問を投げかけ、人間の知性に挑戦する存在だと見なされていると指摘。過去にブルックス氏は、世界経済フォーラムのステージでAIについて挑発的な発言をしたところ、聴衆から「人間を軽視している」という批判を浴びたことがあるそうです。このように、優れたシステムや新たな理論の登場によって「人間の特別さ」が損なわれたと感じる人もいます。
◆AGIは実現できるのか?
2人の会話はAIやロボット工学へと移り、ブルックス氏は「人々が間違った考えに引き込まれてしまうことはよく起きる」という論を展開します。たとえば、アイザック・ニュートンは微積分の発明や運動法則の構築など非常に優れた業績を残しましたが、人生の半分以上を錬金術に費やして鉛を金に変えようとしました。現代人からすると、「なぜニュートンは錬金術なんて愚かなことを信じてしまったのか?」と思うかもしれませんが、これはニュートンが核反応について知らなかったため、鉛を金に変えるには原子核を扱わなければならないという点に気付かなかったからです。つまり、ニュートンは「根本的なモデル」を間違っていたといえます。
また、イーロン・マスク氏はテクノロジー界隈の人間でしたが、宇宙開発企業のSpaceXを立ち上げた際に「Pythonスクリプトを書けば宇宙船を軌道に乗せられる」とは考えませんでした。これは、マスク氏がどんなに大規模なプログラムを書いたところで宇宙船が軌道に乗るわけではなく、燃料の効率的な燃焼や質量、流体力学などについて考えなくてはならないと理解していたからです。
一方で現代人はどういうわけか、「脳内で起きていることは計算である」という思考を持つ傾向があり、AIの計算能力が増せばやがてAGIにたどり着くと考える人も多くいます。しかし、脳で行うすべてのことを可能にするマシンを作るためには、計算能力だけがあれば十分だと証明されたわけではありません。つまり、現状のAIを発展させていくことでAGIにたどり着くという考えは、ニュートンが化学反応によって鉛を金に変えられると考えていたように、根本的な間違いをはらんでいる可能性があるとブルックス氏は指摘しました。
◆製造業の未来はどうなるのか?
マリク氏は中国の製造業が世界のトップを走る一方、アメリカの製造業は衰退していると指摘。「国内の企業がロボットを製造するようになるにはどうすればいいのでしょうか?アメリカの製造業はどうなるのでしょうか?この世界における私たちの位置づけはどうなるのでしょうか?アメリカの製造業の未来について、私たちはどう考えればいいのでしょうか?」と、ブルックス氏にアメリカの製造業について尋ねました。
これに対しブルックス氏は、長らく中国が製造業においてこれほどまでに強力な地位を占めてきたのは、マレーシアやベトナムに構築したサプライチェーンの力が大きいと回答しています。今後、さまざまな機械部品を3Dプリンターで作り出せるようになることを考慮すると、将来のサプライチェーンは3Dプリンターに投入される原材料を中心に展開されるようになり、中国の製造業を強力に支えてきた部品のサプライチェーンの優位性が失われる可能性があるとのこと。
◆ロボット工学とAIについてどう考えるべきなのか?
マリク氏から、「ロボット工学とAIについての正しい考え方とはどのようなものでしょうか?」と尋ねられたブルックス氏は、現時点ではテクノロジーを使って実現するのが難しい課題があるものの、ロボット工学やAIの誇大宣伝ではそれらの問題を軽視していると回答。
たとえば、人々はヒューマノイドロボットが人間のような手で物を操作することに興奮していますが、人間の指が5本であるのは単なる進化上の偶然です。そのため、さまざまな作業をこなすのに人間の手が最適であると考える理由はなく、もしかしたらイソギンチャクのような大量の触手で物体を操作するのが最適であるかもしれません。
ブルックス氏は、「私は最適なロボットについて、人間を複製したものとして考えるべきではないと考えています。人間を複製することが最適な解決策、あるいは最も費用対効果の高い解決策になることは決してありません。ですから、最適なロボットは人間とは異なるものになるでしょう」と述べています。
またAIについても、ブルックス氏はこれまでに何度も流行の移り変わりを経験しており、ニューラルネットワークやエージェントAIの波もやがて衰退する可能性があると指摘。実際、エージェントAIに関する最初の論文が発表されたのは1959年のことであり、エージェントAIは決して目新しいものではないとのこと。
そんな中でブルックス氏は、賢明な人々は生成AIの波が後退した後に残されたデータセンターの活用法を考えていると指摘。「データセンターはただ放置され、利用されるのを待っている状態になるでしょう」「その活用法を誰かが、たとえば若者が見つけ出すことができれば、今まさに無名で貧しい環境にいるその人物が、いずれ大成功を収めるでしょう」とブルックス氏は述べました。
この記事のタイトルとURLをコピーする
ソース元はコチラ
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。