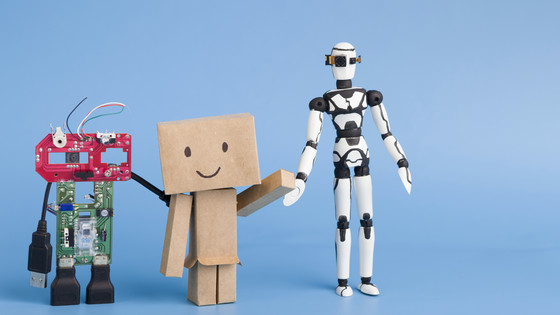Metaの最高技術責任者が同社の将来について、「ハードウェアを製造する他の企業にライセンスを供与するソフトウェアプラットフォームにしたい」というビジョンを語ったことが分かりました。Androidのように、多くのメーカーに使ってもらえるようなソフトウェアの構築を目指すものだとされています。
Humanoid robots are Meta’s next ‘AR-size bet’
https://sources.news/p/humanoid-robots-are-metas-next-ar
Humanoid robots are Meta’s next ‘AR-size bet’ | The Verge
https://www.theverge.com/column/786759/humanoid-robots-meta
Meta wants to become the Android of robotics
https://www.engadget.com/big-tech/meta-wants-to-become-the-android-of-robotics-220701800.html
Metaは2025年9月18日、Ray-Banと組んで展開しているAIグラスの新製品「Ray-Ban Meta」第2世代モデルを発表したばかりで、現実世界へこれまでにない情報をもたらす「AR(拡張現実)」の分野に新たな風を吹かせました。
MetaがAIグラス「Ray-Ban Meta」第2世代モデルと「Meta Ray-Ban Display」を発表 – GIGAZINE
同日発表された高性能スマートグラス「Meta Ray-Ban Display」には、Neural Bandと呼ばれる専用のリストバンドが付属しており、これを付けて空中で手を動かすことで、仮想環境の情報を操作することができます。
MetaのRay-BanディスプレイとNeural Bandの将来についてMetaに聞く – YouTube

MetaはVRヘッドセットの「Meta Quest」などのハードウェアも開発することで知られており、一見するとハードウェア方面に注力しているように思えます。ところが、近年Metaが取り組んでいる人型ロボットの分野に関しては、ハードウェアの製造にとどまらず、ソフトウェア面でも大きな影響力を与えたいと考えていることが幹部の口から明らかにされました。
テクノロジー系メディア「Sources」のインタビューを受けたMetaの最高技術責任者、アンドリュー・ボズワース氏によると、一般的に人型ロボットの開発においてハードウェアの開発は特に障壁ではない一方、ソフトウェアがボトルネックになっていて、人間にとっては簡単な動作をさせるのにも困難が生じているとのこと。
Metaは「Metabot」と呼ばれる人型ロボットを構築中ですが、ボズワース氏はソフトウェアプラットフォームを他社にライセンス供与する構想を描いており、ハードウェアメーカーになることに固執しないことを目指しているそうです。この構想では、Metaが開発したソフトウェア設計図をあらゆる企業が利用できるようになるため、ソフトウェアの開発が進んでボトルネックが解消するものと考えられます。
ボズワース氏は人型ロボットの開発を「今のARレベルの賭け」と称し、数十億ドル(約数千億円)を投じる計画であることを示唆しました。
具体的な取り組みとして、MetaのスーパーインテリジェンスAI研究所とロボティクス部門が協力し、器用な手の動作に必要なソフトウェアシミュレーションを実行できる世界モデルを構築しているとのこと。
過去には、Metaが掃除や洗濯物をたたむといった家事作業をこなせるロボットの開発を検討していると報じられたことがあります。
MetaがAI搭載人型ロボット開発を本格的にスタートか、主に「家事」に焦点を当ててReality Labs内で基盤技術開発チームを編成 – GIGAZINE
ボスワース氏はまた、ロボティクス部門に引き入れたマサチューセッツ工科大学卒のキム・サンベ氏を「現時点で業界最高の戦術ロボティクス専門家」と称賛しているほか、ARグラス「オリオン」のプロトタイプのソフトウェア設計を担当したシニアエンジニア、ユー・ジンソン氏を説得して引退を諦めさせてチームに迎え入れるといった経緯を明かし、「真の成功要因は、当社が引き抜いた人材にある」とも付け加えました。
ロボティクス分野で動いているのはMetaだけではありません。Appleも、詳細は不明ながら「ユーザーの家事を手伝うモバイルロボット」を開発していると伝えられており、AIの次に巨額が投じられるのはロボット技術となるのではないか、との見方があります。
Appleが家庭用ロボットの開発を検討中であると報じられる – GIGAZINE
この記事のタイトルとURLをコピーする
ソース元はコチラ
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。