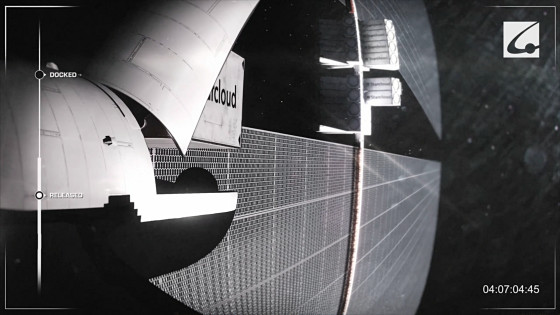by NASA Goddard Space Flight Center
AIの急速な発展に伴い、その計算能力とエネルギーの需要は爆発的に増加しています。Googleは2025年11月4日、宇宙空間でAI(人工知能)の計算能力を大規模に拡張することを目指す新しい研究プロジェクト「Project Suncatcher」を発表しました。これは、AIが人類の最も困難な課題に取り組むための基盤技術であるとの認識に基づいています。
Exploring a space-based, scalable AI infrastructure system design
https://research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/
Project Suncatcher explores powering AI in space
https://blog.google/technology/research/google-project-suncatcher/
データセンターを宇宙に建設する計画は、Googleだけではなくさまざまなスタートアップが実現のために動いています。
宇宙空間にデータセンターを設置する計画が実現間近に – GIGAZINE
Googleの提唱するProject Suncatcherは、太陽系最大のエネルギー源である太陽の力をより効率的に利用する方法を模索するものです。宇宙空間の特定の軌道では、太陽光パネルは地上と比較して年間最大8倍のエネルギーを受け取ることができ、バッテリーの必要性を減らしつつ、ほぼ継続的に電力を生成することが可能です。Googleは、将来的に宇宙がAI計算を拡張する最適な場所になる可能性を見据え、地上の土地や水といった資源への影響を最小限に抑えつつ、この「ムーンショット(壮大な挑戦)」に取り組むとしています。
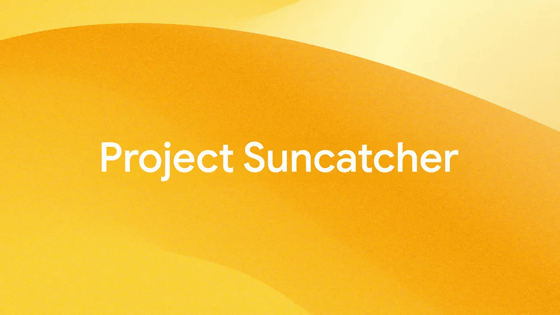
Project Suncatcherの構想は、Google独自のAIアクセラレータチップであるTPUを搭載した人工衛星群を構築するものです。これらの衛星は、発電量を最大化し、地上との通信遅延や打ち上げコストを最小限に抑えるため、全く地球の影に入らないドーンダスク軌道に打ち上げることが想定されています。また、衛星同士は高帯域でネットワーク接続されるため、宇宙空間での組み立てが不要で、小型の衛星を多数連携させるモジュラー(部品組み合わせ型)設計を採用している点が特徴です。これにより、将来的にテラワット級の計算能力を目指す高い拡張性を実現します。
ただし、GoogleはProject Suncatcherを実現するためにはいくつかの主要な技術的課題が存在すると指摘しました。
第一の課題は、衛星間通信の広帯域化です。地上の大規模機械学習クラスターはチップ間で数百Gbps、リンク全体では数Tbps規模の超高帯域通信を行いますが、1~100Gbpsという現在の商用衛星間光リンクのデータレートではこの要求を満たせまないとのこと。そこで、研究チームは、地上の光通信で用いられる「高密度波長分割多重(DWDM)」技術と「空間多重化」の採用を提案しています。
ただし、これらの技術は従来の衛星リンクより数千倍高い受信光パワーを必要とします。受信パワーは距離の2乗に反比例して減少するため、衛星間の距離を数km以下、あるいは数百mといった非常に近い距離で飛行させることで、このパワー要件を満たすとのこと。すでに地上での基礎実験では、単一の送受信機ペアで双方向合計1.6Tbps(片道800Gbps)の伝送に成功しています。

第二の課題は、この高密度な衛星群の制御です。研究では、平均高度650kmで81基の衛星を半径1kmのクラスター内に配置する構成でシミュレーションが行われました。この軌道では地球の重力場の非対称性や大気抵抗が主な外乱要因となりますが、モデルによれば、衛星間の距離が数百mで振動するこの近距離編隊飛行は、太陽同期軌道を維持しつつ、比較的小さな軌道保持操作で実現可能であることが示唆されました。
第三の課題は、宇宙放射線に対するTPUの耐性です。宇宙環境では、累積的な放射線被ばくによるデバイスの劣化や 、単一の高エネルギー粒子による瞬時的な誤動作が懸念されます。特にTPUのような最先端チップの耐性は未知数でした。そこで、GoogleのTPU v6eに対し、低軌道衛星の環境を模して67MeVの陽子ビーム照射試験が実施されました。
その結果、最も敏感だった高帯域幅メモリ(HBM)でさえ、想定される5年間のミッションで受ける放射線量の約3倍に達するまで異常を示さなかったとのこと。チップ自体はさらに強い線量を照射しても永続的な故障が発生せず、TPU v6eは宇宙用途に対して驚くほど堅牢であることが示されたとGoogleは報告しています。SEEについても、HBMでの訂正不能エラーの発生率は非常に低く、軌道上では推論1000万回あたり1回程度と推定され、推論処理には許容可能と見られています。

第四の課題は経済的な実現可能性、特に打ち上げコストです。歴史的に宇宙ベースのシステムの最大の障壁は高い打ち上げコストでした。そこで、Googleは、SpaceXの過去の打ち上げ価格のデータに基づき、「累積打ち上げ質量が倍増するごとに価格が約20%低下する」という学習曲線を分析。この学習率が持続した場合、低軌道への打ち上げコストは2030年代半ばまでに1kgあたり200ドル(約3万円)以下に低下する可能性があると予測しています。
1kgあたり200ドルのコストが実現すると、衛星の打ち上げ費用を耐用年数で割った年間の電力コストは、Starlink v2 mini衛星の試算で約810ドル(約12万2000円)となります。これは、現在のアメリカにおける陸上データセンターの報告されている年間電力コスト約570ドル(約8万5500円)~3000ドル(約45万円)と同等の範囲に収まり、宇宙でのAI計算が経済的に競争可能になることを示唆しています。

今後のステップとして、Googleは2027年初頭までに2基の試作衛星を打ち上げる「学習ミッション」を計画しています。このミッションでは、TPUが宇宙空間でどのように動作するかをテストし、分散型MLタスクにおける光衛星間リンクの有効性を実証する予定です。
将来的には、宇宙空間での効率的な熱管理、地上局との高帯域通信、そして軌道上でのシステムの信頼性確保と修復戦略といった工学的課題に取り組む必要があります。最終的には大規模化と高集積化が宇宙での可能性を前進させ、電力収集や計算、熱管理が緊密に統合された新しい衛星設計へとつながる可能性があるとGoogleは述べました。
この記事のタイトルとURLをコピーする
ソース元はコチラ
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。