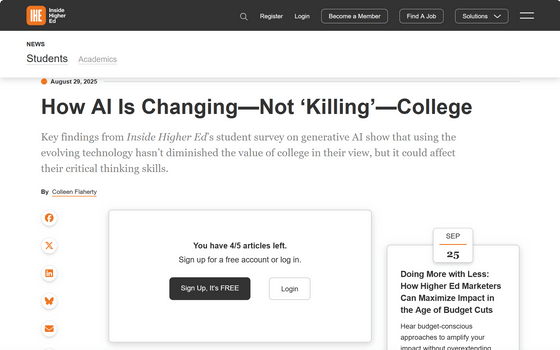大学生を対象にAIについて尋ねた調査で、学生の実に約85%が課題作成に生成AIを使用したと答えたことが分かりました。生成AIを使うことが当たり前になっている世代の実情について、教育関連の出版物を取り扱うInside Higher Edが解説しました。
Survey: College Students’ Views on AI
https://www.insidehighered.com/news/students/academics/2025/08/29/survey-college-students-views-ai
今回の調査では、アメリカにある166の2年制および4年制の大学から1047人の学生の回答が得られました。
回答者のうち、約85%が過去1年間に課題で生成AIを利用したと回答。利用した理由のトップ3は上から順に「アイデアのブレインストーミング(55%)」「チューターとして使う(50%)」「試験・小テストの勉強(46%)」でした。また、高度な検索エンジンのように扱うことも上位(42%)にランクインしました。
基本的には生成AIを学習の補助として使う学生が多く、課題の代行(25%)や論文全体の執筆(19%)に利用したと報告する学生は比較的少なかったそうです。
過去1年間に授業でAIを利用した学生の過半数(55%)は、学習能力と批判的思考力への影響が「一長一短」と回答。時には役立つが、思考の深さを損なうこともあるという意見でした。27%は「実際にプラス効果があった」と回答。効果はマイナスだったと見積もる学生は7%と少数でした。
「過去1年間使用していない」と答えた学生は2年制大学だと21%で、4年制大学(14%)を上回りました。
同級生が学業倫理規定に違反する形で生成AIを使用することを知っている学生に「同級生はなぜそうした使い方をするのか」と尋ねた質問では、「良い成績を取るプレッシャーのため(37%)」「時間的制約のため(27%)」「学術的な誠実さへの無関心(26%)」などが上がりました。
上記の回答は年齢別などさまざまな要因が影響しました。例えば25歳以上の学生は「仕事・家族・その他の義務による時間不足や自身の能力への自信不足」を理由に挙げる割合が若年層より高く、もっと若い学生は「同級生が規範を重視していない」「授業内容との関連性が感じられない」と答える傾向が強いという結果に。
また、回答者の約97%が「生成AIが学業倫理規定へ及ぼす影響について教育機関が対応すべき」だと考えていました。ただ、その方法について「全面使用禁止」と声を上げる人は少なく、支持したのは18%に過ぎませんでした。
教員が生成AIを利用することについては、29%が「思慮深く透明性を持って行われる限り」肯定的に捉えると答えています。14%は教員のAI活用に非常に肯定的で、教育内容の関連性や効率性向上につながると指摘しています。39%の学生はこれにやや否定的あるいは非常に否定的であり、教育の質の低下や生成AIへの過度の依存を懸念しました。残る15%は中立的な意見でした。
また、生成AIが大学という存在そのものの価値に影響を与えたかについては、35%が「変化なし」と答え、23%は「現在より価値が高まった」と回答し、大学の価値に疑問を抱くようになったと答えたのは18%と少数派でした。さらに約4分の1の学生は、「大学の価値に対する考え方は変わったが、その具体的な変化の仕方はわからない」と回答しています。Inside Higher Edは「つまり、生成AIによって学生の目に映る大学の価値が急落したわけではないが、彼らの考え方には明確に影響を与えているのです」と指摘しました。
ミシシッピ大学の学術革新担当副部長マーク・ワトキンス氏は「AIを学業に統合するには、それを正しく指導する機関が必要」と指摘し「適切な利用事例、教職員や管理者を含む全関係者向けの枠組みを公表すべきです」と述べました。
この記事のタイトルとURLをコピーする
ソース元はコチラ
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。