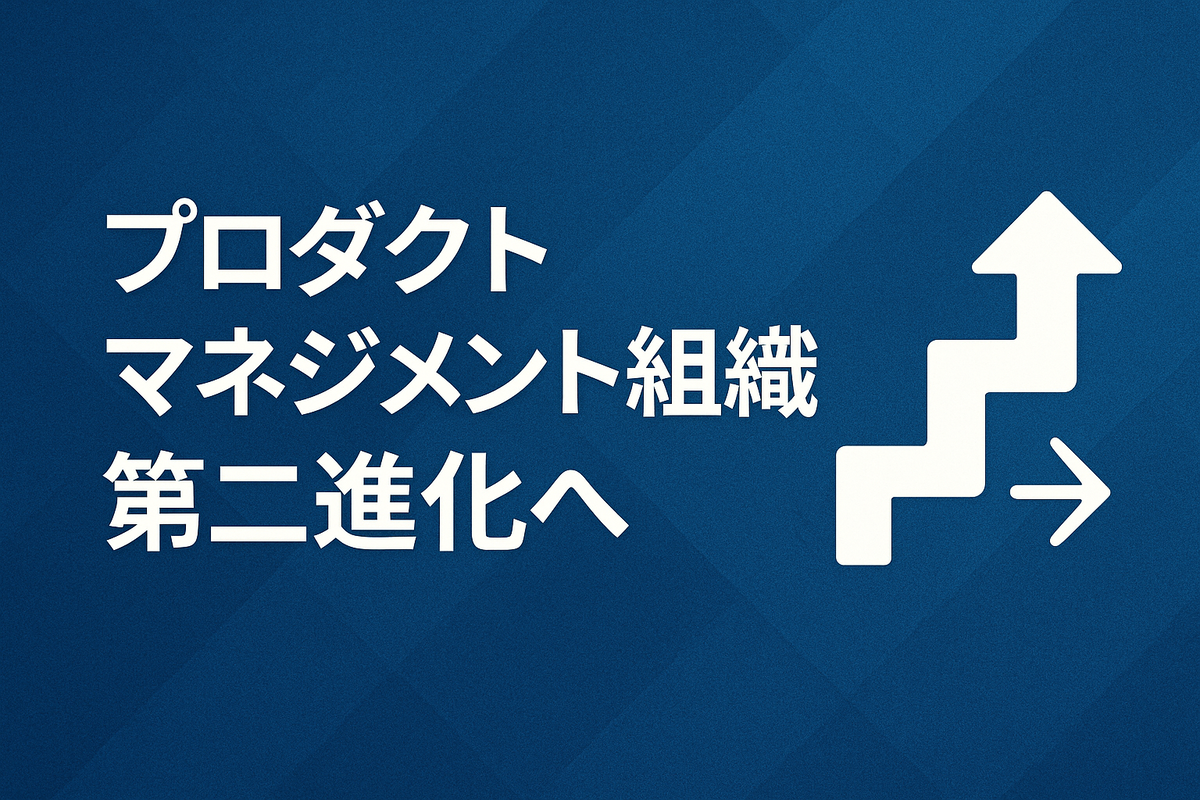
こんにちは、プロダクト部 部長の稲垣です。(自己紹介やこれまでのキャリアについて↓をご覧ください。)
tech-blog.rakus.co.jp
これまで「製品管理課」という名称で運営してきましたが、2025年10月より課を分割し、新しい名称と体制へと進化しました。本記事では、そのご紹介を兼ねてまとめています。
(上位組織である「プロダクト部」については先日まとめましたので、こちらもぜひご覧ください。)
マルチプロダクトを展開し、かつ多様な製品フェーズを抱える企業において、プロダクトマネージャー組織をどのように設計・運営するかを考える上で、一つの参考になればと思います。また、ラクスのプロダクトマネージャーにご興味をお持ちいただいた方にとっても、その意義や背景を感じていただける内容にしていきたいと考えています。
第二進化の背景
当初12名で1つの組織「製品管理課」として活動していましたが、以下の理由から2つの組織に分割し、名称も「プロダクトマネジメント」へ変更しました。組織変更の背景と理由は以下の3点です
- スパン・オブ・コントロール(2ピザルール)の観点
- リーダーPdMへの権限委譲によるプロダクト成長への寄与
- 名称の明確化と統一
それぞれについて解説します。
スパン・オブ・コントロール(2ピザルール)の観点
一般的に、マネージャー1人が効果的にマネジメントできる人数は 5~8名 と言われています。
また、2ピザルール(Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が提唱したルール)では「会議やチームは、2枚のピザでお腹いっぱいになる人数までがちょうど良い」とされています。アメリカのピザを基準にすると、2枚でおおよそ 6〜10人 が食べられる想定です。
ラクスにおいても、この考え方が推奨されており、実際の組織運営に適用されています。特にラクスでは 1on1 や 目標設定・管理 を非常に重視しているため、メンバー数が10名を超えるとチーム成果の最大化に影響が出る可能性があります。
つまり、組織が大きくなると意思決定や管理が複雑化するため、適切な規模に分割することで機動力を維持しやすくしました。
リーダーPdMへの権限委譲によるプロダクト成長への寄与
2024年度からは「楽楽精算」だけでなく、「楽楽明細」「楽楽電子保存」の2つも加わり、プロダクトマネジメントする対象が増えました。これにより、プロダクト部でマネジメントしているプロダクトの合計MRRは 250億円超 となり、相対する開発組織も 70名以上、さらにステークホルダーも 10組織以上 に一気に拡大しました。その結果、一人のマネージャーでは対応に限界が出てきました。
そのため、2024年度下期(10月)からは、リーダーPdMに「楽楽精算」のプロダクトマネジメントのリードを任せ、自分は支援に回る体制に移行しました。この結果、楽楽精算に関してはリーダーPdMが自分以上に高い製品解像度を持つようになり、同年10月にリーダーPdMからMGRへの昇格が決定しました。これを機に、組織を分割することとしました。
つまり、各プロダクトに専任のリーダーPdMを配置し、責任と裁量を持たせることで、よりスピーディーに成長へ貢献できると判断しました。
名称の明確化と統一
記載の通り、開発本部内には「開発管理課」という組織があり、「製品管理」という名称では「プロダクトマネジメント」との関連性が直感的に分かりにくい状況でした。そのため、2025年10月より名称を「プロダクトマネジメント」に変更しました。
もともとは開発本部の横断組織に所属しており、その時はすべて和名で統一されていたため違和感はありませんでした。しかし、プロダクト部に移り、さらに配下に「プロダクトデザイン課」が設置されたことで、和名と英名が混在し、違和感がより強くなっていたことも背景にあります。

第二進化の中身
分割については、製品単位で組織を分ける方針としています。また、対になる開発組織として第一開発統括部内に「楽楽精算開発部」「楽楽明細開発部」があるため、これらと連携を取りやすくする狙いもあります。
※なお、「楽楽明細開発部」は 「楽楽明細」「楽楽電子保存」「楽楽債権管理」 のプロダクト開発を担っています。

プロダクトマネジメント1課
プロダクトマネジメント1課は 「楽楽精算」 を担当しています。役割分担は プロジェクト(PRJ/ミッション)単位 で行っており、1つのPRJは開発規模が大きく、期間も長期にわたるため、2名1チーム で担当する体制を取っています。
プロダクトマネジメント1課の特徴としては以下の4点が挙げられ、これらを踏まえたプロダクトマネジメントが求められます
- 「楽楽精算」は製品フェーズとして、成長期から成熟期へ移行している
- 「楽楽精算」は「楽楽シリーズ」の核となる製品である
- 「楽楽精算」はUXへの課題感があり、さらにシリーズで唯一、ネイティブアプリを有している
- 「楽楽精算」はシリーズの中で最も早く、AI・AIエージェントの取り組みを進めている
プロダクトマネジメント2課
プロダクトマネジメント2課は 「楽楽明細」「楽楽電子保存」「楽楽債権管理」、および プロダクト部内の業務支援 を担当しています。「楽楽明細」は ARR が 100億円に迫る規模 となっており、3名(実質的には1名+0.5名+0.5名) で分担して担当しています。また、プロダクトマネジメント業務のプロセス効率化やAI活用推進 については、「業務支援」がマネージャーと共に担っています。
プロダクトマネジメント2課の特徴としては以下の4点が挙げられ、これらを踏まえたプロダクトマネジメントが求められます。
- 「楽楽明細」は楽楽シリーズの中でも成長著しいプロダクト(2025年3月期:対前年同期比 +45.7%)
- 「楽楽電子保存」は「楽楽明細」との連携が強く、製品特性上、他製品との連携ハブとなる製品である
- 「楽楽債権管理」は2025年7月に販売開始したばかりで、今後 PMF(プロダクト・マーケット・フィット)を目指す製品である
- ラクスのプロダクトマネジメント業務におけるAI活用は現状バラバラに行われており、ノウハウ共有にとどまっている
更なる進化へ
今後、更なる進化を模索していく中で、10月からのプロダクトマネジメント組織において見えている課題は以下の4点です。
- プロダクトマネジメント2課は稲垣が部長と兼務でMGRを務めている
- デザイナー・PMMとの連携がまだ弱い
- 統合型ベスト・オブ・ブリード型の実現に向けたPdM体制が不十分
- プロダクトマネージャーの製品貢献実感および実際の製品成長に大きな余地がある
それぞれについて解説します。
プロダクトマネジメント2課は稲垣が部長と兼務でMGRを務めている
プロダクトマネジメント1課では新しいMGRが誕生しましたが、2課については現在、稲垣が部長と兼務でMGRを担当しています。2課は複数のプロダクトを担当し、さらに業務支援も担うため、1課とは異なる難しさがあります。現状はリーダーPdMに一部を任せつつ伴走していますが、担う役割に対して人数が十分でない ため、新しいリーダーPdMの育成や採用が必要です。
また、今後人数を増やす場合には、スパン・オブ・コントロール(2ピザルール) の観点から、さらに組織を分割する必要が生じる可能性があります。
デザイナー・PMMとの連携がまだ弱い
プロダクト部でプロダクトマネージャーが関わる場合、基本的にこのようなPdM-PMM体制、役割 としています。


両者の役割分担は明確になっていますが、今後はより高い解像度で顧客の課題に向き合い、製販一体 の動きを強化する必要があります。そのため、PdM自身がPMM領域の知識を学び、自ら情報をキャッチアップしていくことが求められます。

また、目指すべき姿をこのように定義していますが、デザイナーとの連携についても強化の余地が大きく、UXやデザインの知識に深く関与できるPdMが必要です。今後は、より多様な人材の登用 も視野に入れるべきと考えています。
統合型ベスト・オブ・ブリード型の実現に向けたPdM体制が不十分
現在、楽楽シリーズでは、これまでの 「ベスト・オブ・ブリード型」戦略 をアップデートし、「統合型ベスト・オブ・ブリード」 のプロダクトを目指しています。その実現に向けて、PMM側では 「マルチプロダクト戦略課」 を立ち上げ、戦略を前に進める取り組みを始めています。(詳細はこちら
note.com
へ)
一方で、PdM側ではまだ十分に呼応する体制が整っていません。今後、この戦略に対応したPdMを配置することで、より効果的に機能する可能性があると考えています。
現状では、連携の中心となるプロダクトが「楽楽精算」や「楽楽明細」であり、これらを担当するPdMがその役割を担っています。しかし、今後は 単独のドメインや個別プロダクトにとどまらず、より広い視野と先を見通す力を持つPdM が必要です。そのために、少しずつ準備を進めています。
プロダクトマネージャーの製品貢献実感および実際の製品成長に大きな余地がある
2024年度下期から、プロダクトマネージャーに対して 製品貢献実感 に関するアンケートを実施しています。※アンケート内容や詳細については「(2)製品貢献実感は、まだまだ伸びしろあり」を参照してください。
担当プロダクトは ARR規模が大きく、関わるステークホルダーも多いため、貢献実感を得にくい 側面があります。そのため、プロダクトマネージャーがしっかりと貢献実感を持てるような取り組みを進めつつ、実際の製品成長をさらに加速させること を目指していきます。
最後に
11月(大阪)、12月(東京)に開催される 「PM Conf 2025」 において、当社ラクスのPdMから2名が公募セッションに採択されました。ここでもご紹介しておきます。
大阪開催 植木遼太 (シニアPdM)
私とほぼ同期で入社し、一度退職後にラクスへ再入社していますシニアPdMとして多様な経験を積んできており、その知見を今回のセッションでお話しする予定です。
関連ブログ:ブーメラン転職ってどうなの?実体験から語る
tech-blog.rakus.co.jp
東京開催 紀井 美里 (リーダーPdM)
プロダクトマネジメント2課のリーダーPdMとして活躍中です新卒でラクスに入社して約10年、「楽楽精算」の開発・PdMを担当後、現在は別プロダクトを担当しています。さらにPdMの育成にも尽力しており、その取り組みを今回発表する予定です。
関連ブログ:AI時代のプロダクトマネージャー:組織と人材の変化から見る新しい価値創造
tech-blog.rakus.co.jp
/ 個の限界が教えてくれたマネジメントへの道:葛藤を超えて形作る自分だけのキャリア
tech-blog.rakus.co.jp
私の挑戦
私自身も昨年に続きプロポーザルを出しましたが、残念ながら今回は落選しました。まだ2回目の挑戦なので、来年もチャレンジするつもりです。ただし徐々にプロダクトマネジメントの現場から離れつつあるため、来年が最後のチャンスかもしれない と感じています。
今回応募したテーマは以下の通りで、今後どこかの機会でお話しできればと思っています。
- 組織戦略・キャリア・役割分担
意思決定とアライン
「2)次の進化にむけて」でも触れましたが、ラクスのプロダクト部では現在 プロダクトマネージャーを積極的に採用中 です。本noteを読んで当社プロダクト部に興味を持っていただいた デザイナーやプロダクトマネージャーの方 は、ぜひカジュアル面談からでもご応募ください。
※プロダクトマネージャーのカジュアル面談は、基本、私(稲垣)が担当しています。
●採用情報
プロダクトマネージャー
career-recruit.rakus.co.jp
デザイナー
career-recruit.rakus.co.jp
└ デザインマネージャー
career-recruit.rakus.co.jp
/アシスタントマネージャー
career-recruit.rakus.co.jp

