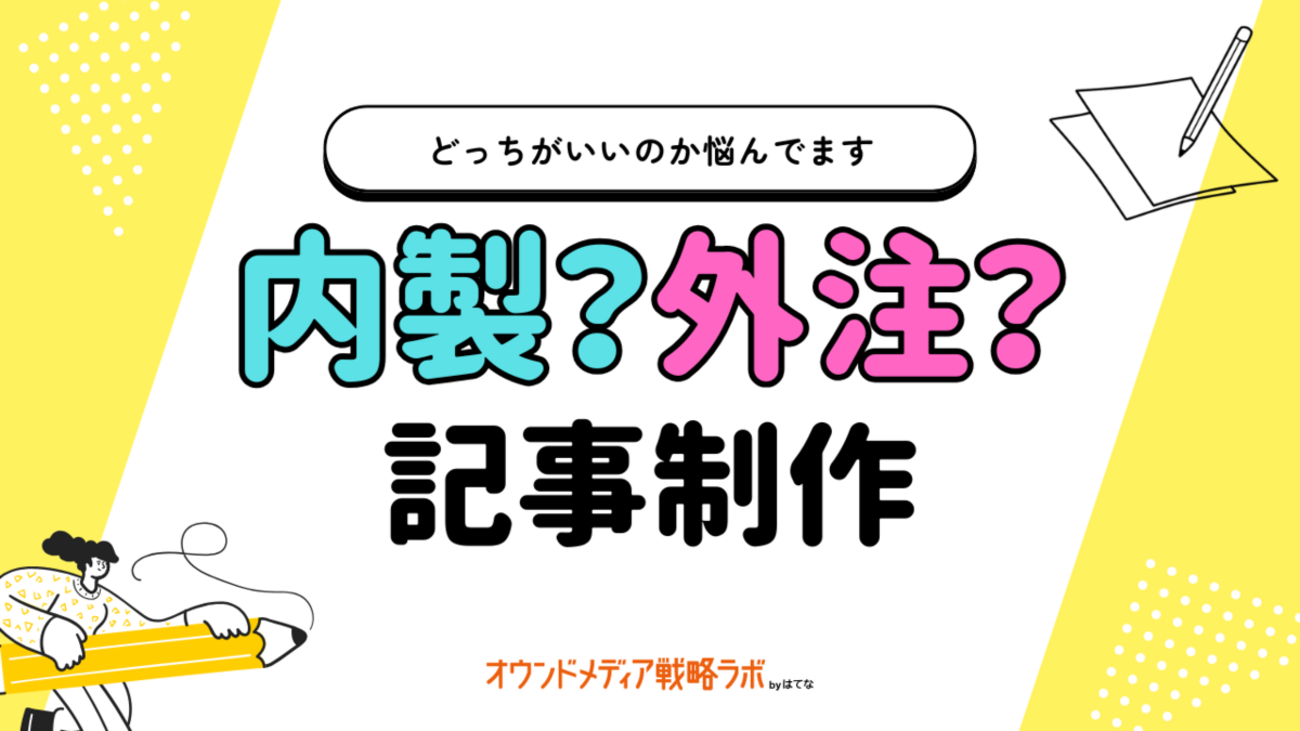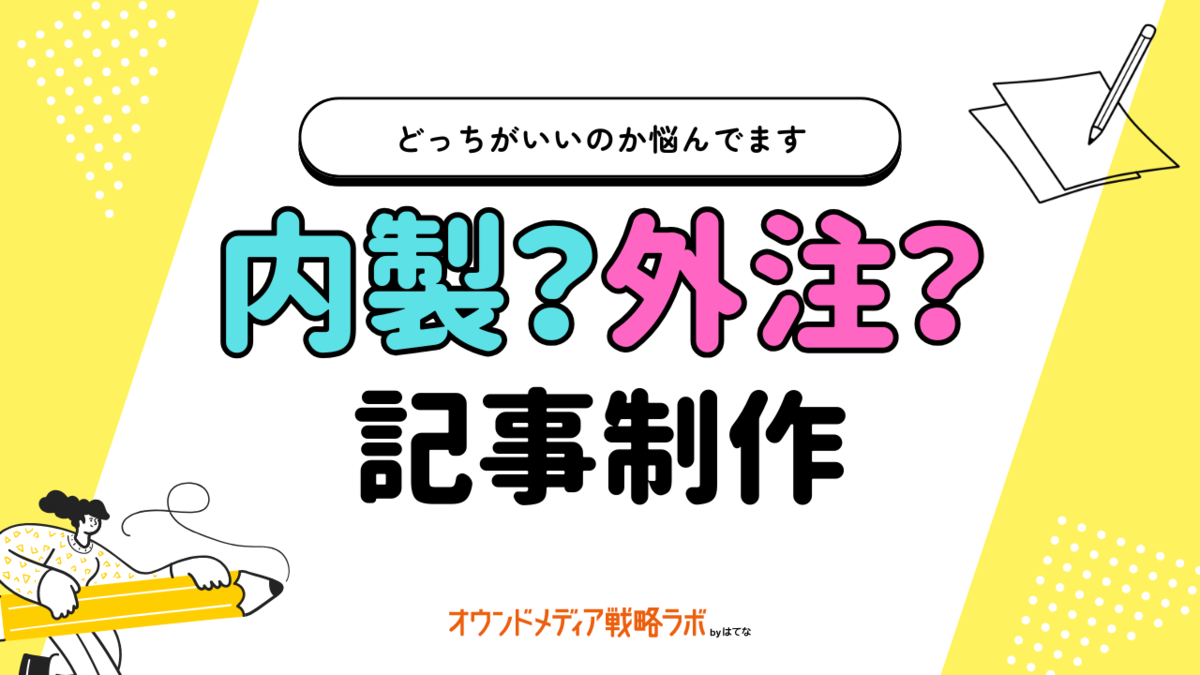
オウンドメディアの成果を最大化するために、記事制作は欠かせない要素です。
しかし、日々の業務に追われる中で、「質の高い記事を安定的に供給し続けるのが難しい」「そもそもどのような記事を作れば成果に繋がるのかわからない」といった悩みを抱える担当者様は少なくありません。
特に近年、AI技術の進化により、記事制作の選択肢はさらに多様化・複雑化しています。AIを活用すれば内製でも十分ではないか?」「いや、こんな時代だからこそプロに外注すべきなのか?」その判断に迷われている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、AI時代の記事制作における「内製」と「外注」のメリット・デメリットを徹底比較します。 さらに、強みの異なる記事制作代行会社の3つのタイプや、自社の目的に合わせた選び方を解説。 成果を出すためのコンテンツの条件についても掘り下げていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
-
この記事はこんな人におすすめ
- オウンドメディアを運営しているが、質の高い記事を安定して制作するリソースがない方
- 記事制作を内製すべきか外注すべきか、それぞれのメリット・デメリットを知りたい方
- 自社の目的に合った、最適な記事制作のパートナーを見つけたい方
AI時代の記事制作|内製と外注のメリット・デメリット

AIの登場により、コンテンツ制作のハードルは大きく下がりました。しかし、それは必ずしも「誰でも簡単に成果を出せる」ことを意味しません。
むしろ、AIをいかに活用し、戦略に組み込むかが新たな課題となっています。まずは、現代の記事制作における「内製」と「外注」、それぞれのメリット・デメリットを客観的に整理してみましょう。
【内製】AIで効率化は可能。しかし「戦略」と「品質管理」の属人化が課題
内製の一番のメリットは、自社製品やサービスへの深い理解に基づいた、熱量の高いコンテンツを制作できる点にあります。
社内の担当者であれば、企業の文化やブランドイメージを正確に反映し、一貫性のあるメッセージを発信することが可能です。また、外注にかかる費用を抑えられるというコスト面での利点や、コミュニケーションが円滑でスピーディーな意思決定ができる点も魅力です。
AIライティングツールを活用すれば、これまで作成に時間がかかっていた記事のドラフト作成や情報収集といった作業を大幅に効率化できます。これにより、担当者はより創造的な業務、例えば企画や編集、効果測定といった部分に集中できる時間が増えるでしょう。
しかし、その一方で大きな課題も存在します。
それは「戦略」と「品質管理」が、担当者のスキルや経験に大きく依存してしまう「属人化」のリスクです。
SEOで成果を出すためには、キーワード選定から構成案の作成、競合分析、そして読者の検索意図を深く理解した上でのライティングまで、高度な専門知識が求められます。AIは文章を生成できても、事業成果に繋がるコンテンツ戦略そのものを描くことはできません。
また、AIが生成した文章には、情報の正確性の欠如や、独自の視点・一次情報の不足、ブランドイメージにそぐわない表現といった問題が含まれる可能性があります。
これらを見極め、適切に編集・修正する「品質管理」の能力がなければ、AIの利用はかえってブランドの信頼性を損なう危険性すらあります。
担当者の異動や退職によって、メディア全体の品質が大きく左右されるリスクは、内製体制が常に抱える課題と言えるでしょう。
【外注】AIを使いこなす専門家による「戦略的アウトプット」が魅力
外注の最大のメリットは、記事制作のプロフェッショナルが持つ専門知識と経験を活用できる点です。
彼らは、SEOの最新トレンドを常に把握し、データに基づいた戦略的なキーワード選定や、読者の心を動かす高品質な記事制作のノウハウを持っています。
AIを単なる文章生成ツールとしてではなく、競合分析や構成案作成の効率化、多角的な視点の洗い出しなど、戦略を補強するための「アシスタント」として高度に使いこなします。
これにより、自社で専門人材を育成する時間とコストをかけることなく、即戦力となるリソースを確保できます。
結果として、記事制作にかかる社内リソースを大幅に削減し、担当者様はより重要な業務、例えばコンテンツ全体の戦略策定や、生み出されたリードへのアプローチといったコア業務に集中することが可能になります。
もちろん、外注にはコストがかかるというデメリットがあります。
また、自社の製品やサービス、ブランドの価値観を外部のライターに正確に理解してもらうためのコミュニケーションコストも発生します。依頼先によっては、品質にばらつきがあったり、期待していた成果物が得られなかったりするリスクもゼロではありません。
しかし、これらのデメリットは、信頼できるパートナーを慎重に選定することで最小限に抑えることが可能です。
長期的な視点で見れば、専門家の知見を活用して生み出される「成果の出るコンテンツ」は、新たな顧客を呼び込み続ける強力な資産となり、結果的にコストを上回る価値を生み出す可能性を秘めています。
結局「内製」と「外注」どちらを選ぶべき?
ここまで内製と外注のメリット・デメリットを見てきましたが、最終的にどちらを選ぶべきなのでしょうか。その判断の分かれ目となるのは、「記事制作の目的」と「社内リソース」の2つの軸です。
もし、記事制作の目的が社内情報の共有や、ごく一部の既存顧客に向けた情報発信であり、かつ社内にコンテンツ戦略から品質管理までを一貫して担える専門知識を持った人材がいるのであれば、AIを活用した内製でも十分かもしれません。
しかし、「オウンドメディアを通じて新規顧客を獲得したい」「検索エンジンで上位表示させ、事業の売上に貢献したい」といった明確な事業目標があり、かつ社内に専門スキルを持つ人材が不足している、あるいは担当者が他の業務で手一杯という状況であれば、専門家の力を借りる「外注」が極めて有効な選択肢となります。
特にAI時代においては、ただ記事を「作る」だけでは競合との差別化は困難です。
AIを使いこなした上で、さらにその先にある「戦略」や「独自性」をいかにコンテンツに盛り込めるか。その視点を持つと、外注という選択肢の価値がより明確に見えてくるのではないでしょうか。
内製か外注か、その答えが見えてきたところで、次に気になるのは「では、外注するならどこに頼めば良いのか?」という点でしょう。
次の章では、記事制作会社のタイプを具体的に解説し、貴社に最適なパートナーを見つけるためのヒントを提供します。
記事制作会社は、強みの異なる3タイプに大別される

一言で「記事制作会社」と言っても、その特徴や強みは様々です。自社の目的や予算に合わない会社を選んでしまうと、「コストはかかったのに成果が出ない」という事態に陥りかねません。ここでは、数多く存在する記事制作会社を、その提供価値によって大きく3つのタイプに分類し、それぞれの特徴を解説します。
タイプ1:コストと量を最適化する「クラウドソーシング・個人特化型」
このタイプは、主にクラウドソーシングプラットフォームなどを活用し、多数の登録ライターに記事制作を依頼する形態です。最大の魅力は、比較的安価に、そして大量の記事をスピーディーに制作できる点にあります。
例えば、「まずはメディアの記事数を増やして、サイトの土台を作りたい」「特定のジャンルに特化した記事をとにかく量産したい」といったニーズには非常に有効です。予算が限られている場合や、短期間で大量のコンテンツが必要な場合には、有力な選択肢となるでしょう。
ただし、注意点もあります。このタイプのサービスでは、ライターのスキルや専門性にばらつきが出やすい傾向があります。
そのため、深い専門知識が求められる記事や、企業のブランドイメージを大きく左右するような重要なコンテンツの制作には、慎重な判断が必要です。
あくまでも「量を確保するための手段」と割り切り、戦略設計や最終的な品質管理は自社で厳密に行うことを前提として活用するのが成功の鍵となります。
タイプ2:戦略と品質で「事業成果」を追求する「コンテンツマーケティング型」
このタイプは、単に記事を制作するだけでなく、その前段階である「戦略設計」から、公開後の「効果測定・改善」までを一気通貫で支援することを強みとしています。彼らは、オウンドメディアを事業成長のための重要な「マーケティング施策」と位置づけ、成果に徹底的にこだわります。
具体的には、市場調査や競合分析、ペルソナ設計、キーワード戦略などを通じて、「誰に、何を、どのように伝えれば、最終的なコンバージョン(売上)に繋がるのか」という問いに、データと経験に基づいて答えてくれます。制作される記事は一本一本が戦略に基づいて練り上げられており、その品質は非常に高いものになります。
AIを戦略立案の補助や効率化のツールとして活用しつつも、最終的なアウトプットは経験豊富なディレクターや編集者が責任を持つため、独自性や専門性、そしてブランドイメージを損なわないコンテンツ制作が可能です。
初期コストは他のタイプに比べて高くなる傾向がありますが、長期的に見れば、質の高い記事が資産となり安定した集客と売上を生み出し続けるため、最も費用対効果が高くなる可能性があります。
「本気でオウンドメディアで成果を出したい」「事業の成長に貢献するコンテンツが欲しい」と考える企業にとって、最も信頼できるパートナーとなるでしょう。
タイプ3:「広告」や「SNS」と連携させ、相乗効果を生む「総合代理店型」
このタイプは、記事制作を単体で請け負うというよりは、Web広告やSNS運用、サイト制作、イベント企画など、デジタルマーケティング全般の施策の一つとしてコンテンツ制作を提供する形態です。
最大のメリットは、様々なマーケティング施策との連携がスムーズである点です。例えば、広告で集客したユーザーの受け皿として記事コンテンツを用意したり、SNSで話題化させるための企画を記事と連動させたりと、一貫したマーケティング戦略の中でコンテンツを効果的に活用することができます。複数の業者とやり取りする必要がなく、管理コストを削減できる点も魅力です。
一方で、注意すべきは、彼らの専門領域が広範にわたるため、必ずしも「コンテンツ制作」そのものが最も得意な領域とは限らないケースがある点です。SEOの深い知見や、特定の業界に関する専門性、読者の心を動かす編集力といった点では、「コンテンツマーケティング型」の専門会社に一歩譲る可能性も考慮しておく必要があります。Webマーケティング全体を包括的に任せたい、という場合に最適な選択肢と言えるでしょう。
これら3つのタイプを理解することで、自社の目的や課題に合った依頼先が明確になったのではないでしょうか。しかし、AIの進化が著しい現代において、本当に成果を出すコンテンツとはどのようなものなのか、その本質を理解しておくことも重要です。
AI時代に成果を出すコンテンツの条件

AIライティングツールを使えば、誰でも手軽に文章を作成できるようになりました。しかし、それは「成果の出るコンテンツ」を誰でも作れるようになった、という意味ではありません。むしろ、情報が溢れる今だからこそ、ユーザーや検索エンジンから真に評価されるコンテンツの条件は、より厳しく、そして明確になっています。
AIは「量産」できても「戦略や独自コンテンツ」は作れない
AIの最も得意とするところは、既存の情報を学習し、それを組み合わせて新しい文章を生成することです。指示さえすれば、平均的な品質の記事を、人間とは比べ物にならないスピードで大量に生み出すことができます。この「量産」能力は、コンテンツ制作の効率化において非常に強力な武器となります。
しかし、AIには決定的に作れないものがあります。それは、企業の事業目標に紐付いた「戦略」と、読者の心を揺さぶる「独自コンテンツ」です。AIは、なぜこのキーワードで上位表示を目指すのか、その先にどのような顧客との関係構築を描くのか、といったビジネスの根幹に関わる戦略を自ら描くことはできません。
また、AIが生成する文章は、あくまでインターネット上に存在する情報の再構築に過ぎません。そのため、自社独自の調査データや顧客へのインタビュー、専門家としての深い洞察、社員の体験談といった、他にはない一次情報に基づいた「独自コンテンツ」を生み出すことは原理的に不可能なのです。
検索エンジンが評価するのは「E-E-A-T」を満たした独自コンテンツ
Googleをはじめとする検索エンジンは、近年「E-E-A-T」という品質評価基準を重視しています。これは、「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字を取ったものです。
検索エンジンは、単に情報が網羅されているだけの記事よりも、実際に製品を使った経験や、専門家としての知見、そしてその情報が信頼できるものであることを示す証拠が含まれた記事を高く評価します。これはまさに、AIが生成した平均的なコンテンツとは一線を画す要素です。
結局のところ、検索エンジンが目指しているのは、ユーザーにとって最も価値のある情報を提供することです。情報が氾濫し、AIによるコンテンツが増えれば増えるほど、他では得られないユニークな価値を持つ「独自コンテンツ」の重要性は、ますます高まっていくでしょう。
戦略を描ける「専門家」の価値が高まる
このような状況において、相対的に価値が高まっているのが、戦略を描き、独自コンテンツを生み出すことができる「専門家」の存在です。
AIを単なる文章作成ツールとしてではなく、競合分析やアイデア出しを効率化するための優秀なアシスタントとして使いこなし、人間はより創造的で戦略的な業務に集中する。
具体的には、市場のニーズを深く洞察し、競合との差別化ポイントを見出し、自社ならではの価値をどのようにコンテンツに落とし込むか、という戦略を設計する。そして、その戦略に基づいて、読者の感情に訴えかけ、行動を促すような質の高いコンテンツを企画・編集する。
AI時代にオウンドメディアで成果を出すためには、こうした高度なスキルを持つ専門家とのパートナーシップが、かつてないほど重要になっているのです。
では、具体的にどのような基準で記事制作のパートナーを選べば良いのでしょうか。次の章では、これまで解説してきた3つの会社タイプごとに、具体的な選び方のポイントを解説します。
【目的別】記事制作代行会社の選び方
自社の目的によって、選ぶべき記事制作代行会社は大きく異なります。ここでは、「コストを抑えたい」「マーケティング全体を任せたい」「売上を本気で伸ばしたい」という3つの目的別に、最適な会社のタイプと、その選び方のポイントを具体的に解説します。
コストを抑えて記事数を増やしたいなら「クラウドソーシング・個人特化型」
こんな企業におすすめ
- とにかく予算が限られている
- メディア立ち上げ初期で、まずはコンテンツの量を確保したい
- 社内にディレクションと品質管理ができる人材がいる
選び方のポイント:
コストを最優先し、記事の量を確保したい場合は、「クラウドソーシング・個人特化型」のサービスや、フリーランスのライターへの直接依頼が選択肢となります。
このタイプを選ぶ上で最も重要なのは、発注者側、つまり自社に「ディレクション能力」と「品質管理体制」が備わっているかどうかです。
どのようなキーワードで、どのような構成の記事を作成してほしいのかを具体的に指示できなければ、期待通りの成果物は得られません。また、納品された記事が事実に基づいているか、コピーコンテンツになっていないか、レギュレーションを遵守しているかなどをチェックする体制も不可欠です。
安価に大量の記事を制作できる魅力は大きいですが、それはあくまで自社で品質をコントロールできることが大前提です。量を確保するための手段と割り切り、戦略設計や品質管理は自社で行うという明確な役割分担のもとで活用することが成功の鍵となります。
マーケティング全体を任せたいなら「総合代理店型」
こんな企業におすすめ
- Web広告やSNSなど、他の施策と連携させたい
- 複数の業者とのやり取りを一本化し、管理コストを削減したい
- マーケティング全体の戦略から相談したい
選び方のポイント:
記事制作だけでなく、Webマーケティング全体の最適化を目指すのであれば、「総合代理店型」の会社が頼りになります。彼らは各施策の専門家を社内に抱えており、一貫したマーケティング戦略を実行できるのが強みです。
このタイプを選ぶ際は、担当者との連携が密に取れるか、そして自社の事業や業界への理解度が高いかを見極めることが重要です。また、彼らの得意領域が広告運用なのか、サイト制作なのか、それともコンテンツ制作なのか、ポートフォリオや実績をよく確認し、自社が最も重視する領域と合致しているかを確認しましょう。
コンテンツ制作の専門性が最優先事項ではない場合もあるため、その点は注意が必要です。
売上を本気で伸ばしたいなら「コンテンツマーケティング型」一択の理由
こんな企業におすすめ
- オウンドメディアからの問い合わせや資料請求を増やしたい
- コンテンツを会社の「資産」として、長期的に集客できる仕組みを作りたい
- 専門性が高く、競合と差別化できる記事が必要
選び方のポイント:
サイトからの問い合わせや資料請求、サービスの導入といった「売上」に直結する成果を本気で目指すのであれば、選ぶべきは「コンテンツマーケティング型」一択と言えるでしょう。
AIがどれだけ進化しても、読者の課題に深く共感し、心を動かし、最終的な行動へと導くコンテンツには、専門家による緻密な戦略と、人の手による品質向上が不可欠です。このタイプの会社は、まさにその価値を提供してくれます。創造性を最大限に発揮し、競合との差別化、独自の価値提案、ブランドストーリーの構築といった、事業の根幹を支えるコンテンツを生み出すことを得意としています。
初期コストは高く見えるかもしれませんが、長期的に見れば、質の高い記事が検索エンジンから評価され続け、安定した集客チャネルとして機能します。これは、広告のように費用をかけ続けなければ効果が途切れてしまう施策とは異なり、まさに「資産」となる投資です。そのため、結果的に費用対効果が高い選択と言えます。
【コンテンツマーケティング型の成功事例】人材企業A社様
専門家の知見を独自コンテンツ化し、3週間で約30万PVを獲得
ここでは、AIでは生成できない専門的なコンテンツをはてなが企画・制作し、大きな成果を上げた「コンテンツマーケティング型」の成功事例をご紹介します。
企画の狙い:
多くのビジネスパーソンが抱える普遍的な悩みである「職場の人間関係」に着目し、「◯◯な人への対処法」という、検索ニーズはありながらも、一般的なノウハウ記事が溢れているテーマを扱いました。
ここでの狙いは、AIが生成するようなありふれた内容ではなく、専門家の学術的な知見を基にした信頼性と独自性の高いコンテンツを制作すること。 これにより、読者に深い示唆を与え、メディアの価値を向上させることを目指しました。
記事制作で行ったこと:
「◯◯な人への対処法」という概念そのものをアカデミックな視点から解説するため、心理学者の大学教授にインタビューを実施しました。 個人の主観や経験談に頼るのではなく、「専門家に見解を問う」という編集方針で企画を立案し、一次情報に基づいた記事を制作しました。
これにより、読者が職場の人間関係を異なる視点から捉え直すきっかけとなる、個性的で深みのあるコンテンツが完成しました。
結果:
この記事は公開後、大きな反響を呼びました。
- PV数: 公開から約3週間で約30万PVを獲得しました。
- 拡散: はてなブックマークで600以上のブックマークを集め、コメント欄では読者それぞれの体験談や意見が活発に交わされました。
- 外部流入: はてなブックマークを起点に、SmartNewsやGoogle Discoverにも掲載され、オーガニック流入で広く読者を獲得しました。 特にGoogle Discoverからの流入はクリック数12万以上、表示回数150万回を超える記録的な数値となりました。
この事例は、AIだけでは決して生み出せない「専門家の知見」という付加価値を、適切な企画・編集によって独自コンテンツへと昇華させることで、ユーザーから圧倒的な支持を得られることを証明しています。
「コンテンツマーケティング型」の重要性をご理解いただけたところで、最後に、数ある専門会社の中から、真に信頼できるパートナーを見つけ出すための具体的なポイントを3つご紹介します。
「コンテンツマーケティング型」の選び方3つのポイント
事業成果にコミットする「コンテンツマーケティング型」の会社は、まさにオウンドメディア運営の強力なパートナーとなります。しかし、その中から自社に最適な一社を見つけ出すには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。ここでは、後悔しないパートナー選びのために、特に重視すべき3つのポイントを解説します。
1:支援実績に「自社と近い業界・課題」があるか
まず確認すべきは、その会社が持つ支援実績です。特に、自社と同じ、あるいは近い業界での実績があるかどうかは非常に重要な判断基準となります。
BtoBとBtoCでは読者の意思決定プロセスが全く異なりますし、金融、医療、不動産といった専門性が高く、情報の正確性が厳しく問われるYMYL(Your Money or Your Life)領域では、業界特有の知識や法律への理解が不可欠です。
過去の実績の中に、自社が抱える課題、例えば「専門的な内容を分かりやすく伝えたい」といった課題に近いケースを解決した事例があるかを確認しましょう。
具体的な事例を提示してもらい、どのような課題に対して、どのような戦略とコンテンツでアプローチし、最終的にどのような成果が出たのかを詳しくヒアリングすることが、ミスマッチを防ぐための第一歩です。
2:記事の品質を担保する「編集・校閲体制」は盤石か
AI時代において、高品質な記事はライターの執筆スキルだけで生み出されるものではありません。 ライターが執筆した原稿を客観的な視点でチェックし、より分かりやすく、より説得力のある内容へと昇華させる「編集者」や、最終的な品質に責任を持つ「ディレクター」の存在が不可欠です。
AIが生成した文章のファクトチェックや、誤った情報の修正、ブランドイメージに沿ったトーン&マナーの統一など、その役割は多岐にわたります。
依頼を検討している会社に、「どのような制作体制で記事が作られているのか」を必ず確認しましょう。
執筆、編集、校閲といった各工程で、複数の担当者が異なる視点からチェックするフローが確立されていれば、安定して質の高い記事を制作してくれる可能性が高いと判断できます。
3:公開後の分析・改善まで見てくれるか
記事制作は、コンテンツをWebサイトに公開して終わりではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。 公開した記事が、検索順位や流入数、そして最終的なコンバージョン数にどのような影響を与えているのかを数値で分析し、改善を繰り返していくサイクルが不可欠です。
したがって、「作って終わり」ではなく、公開後の効果測定を行い、その結果に基づいて「次の一手」となる改善提案までしてくれる会社を選ぶことが重要です。 定期的なレポート提出やミーティングの機会があるか、どのようなツールを使って分析を行うのかなどを事前に確認しましょう。
記事制作から次の戦略提案までを一貫して任せられるパートナーを見つけることができれば、オウンドメディアの成長は格段にスピードアップするはずです。
成果を出す記事制作ならはてなにお任せください!
AI時代の記事制作における外注と内製の比較、そして成果を出すためのパートナー選びのポイントについて解説してきました。
リソース不足やコンテンツの品質に課題を感じ、信頼できる専門家を探しているご担当者様も多いのではないでしょうか。もし、事業成果にコミットする記事制作パートナーをお探しなら、ぜひ株式会社はてなにご相談ください。
私たち株式会社はてなは、「コンテンツマーケティング型」の支援を得意とするプロフェッショナル集団です。
- 戦略設計からコミット:貴社の事業課題を深く理解し、単なる記事制作に留まらない、ビジネスゴール達成から逆算したコンテンツ戦略を設計します。
- 編集力と専門性:月間数千万人が利用する「はてなブログ」や「はてなブックマーク」の運営で培った編集ノウハウと、各業界の専門家ネットワークを活かし、他社には真似できない独自性と品質の高いコンテンツを生み出します。
- データに基づいた改善提案:公開後の効果測定を徹底し、データに基づいて次の一手を提案。継続的なPDCAサイクルで、オウンドメディアを「成果の出る資産」へと育て上げます。
「何から手をつければいいかわからない」「今の運用方法で本当に成果が出るのか不安だ」
もし、あなたがそんな悩みを抱えているなら、まずは一度、私たちにお話を聞かせてください。貴社の課題に寄り添い、事業を成功に導くための最適なプランをご提案します。
はてなでは、経験豊富なスタッフがオウンドメディアの計画から記事制作、システム、集客、分析まですべてをサポートいたします。オウンドメディア戦略ラボでは、これまでのオウンドメディア支援で培った知見やノウハウをお届けします。
Web:オウンドメディア戦略ラボ