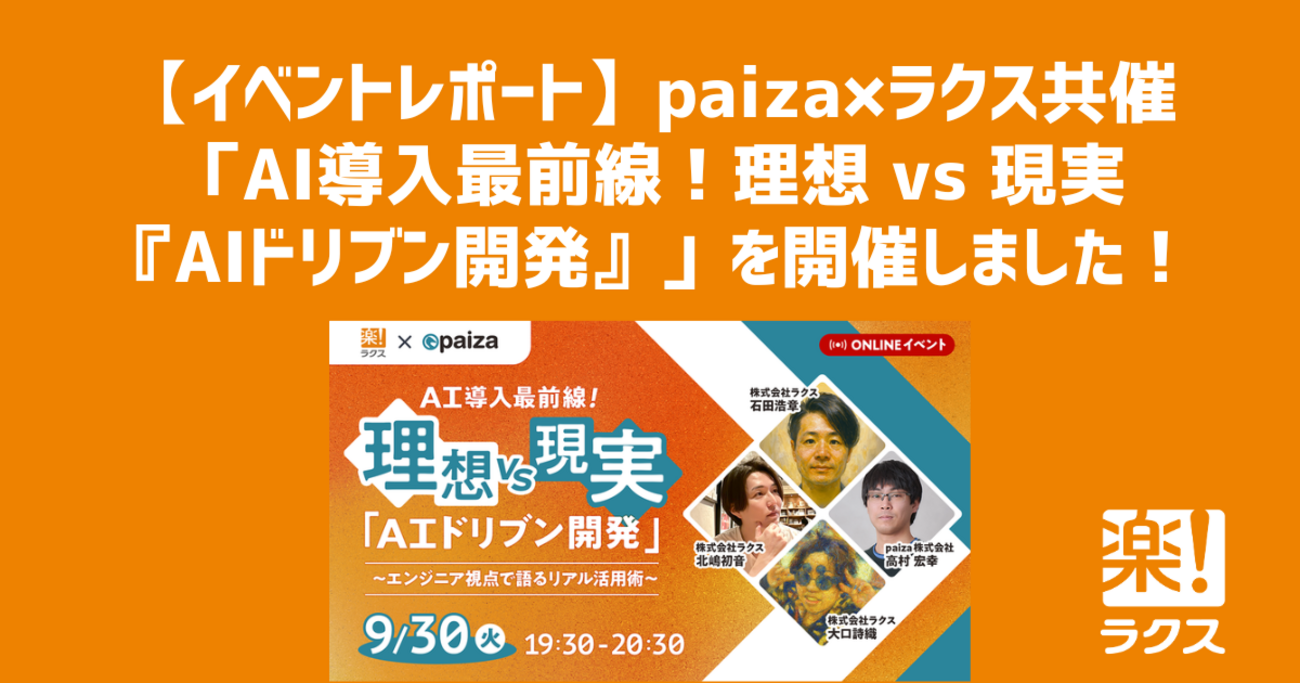202025年9月30日(火)、paiza株式会社と株式会社ラクスは、共同技術イベント「AI導入最前線!理想 vs 現実『AIドリブン開発』 〜エンジニア視点で語るリアル活用術〜」を開催しました。
「AIが自動でコードを書いてくれる」「開発効率が劇的に上がる」といった輝かしい「理想」の一方で、開発の現場では多くのエンジニアが現実的な課題に直面しています。
本イベントでは、AI開発の最前線で活躍する4名の登壇者が、実際に直面した困難や、それを乗り越えるために生み出したリアルな解決策を共有しました。
全てのセッションに共通するキーワードは「コンテキスト(文脈)」。AIの真価をいかに引き出すか、その実践的なヒントが満載のイベントの様子をレポートします!
登壇者:株式会社ラクス 石田 浩章
AI活用の第一歩は、個人のスキルや熱意といった「点」を、いかにして組織全体の「面」の強さに変えていくか、という課題にあります。
このセッションでは、ラクス社がAIツールの導入初期に直面した「活用レベルが個人の意欲に依存し、社員間の格差が生まれてしまう」という課題から、いかにして脱却したかが語られました。
取り組みのポイント
- 推進体制の構築: 各チームのリーダーによる「推進チーム」と、現場の旗振り役となる「推進役」を設置し、トップダウンとボトムアップを組み合わせた体制を構築。
- 「まず実践」の文化醸成: 完璧な計画を待つのではなく、「まずやってみよう」という文化を徹底し、実践から得られる学びを重視。
- 知見の共有サイクル: 各チームの成功・失敗事例をリーダーが集約し、汎用的な知見として全体に共有する学習サイクルを確立。
この4ヶ月間の取り組みの結果、AIツールの実務利用率は80%から100%に向上。さらに注目すべきは、自発的な情報共有の活動量が34%も向上した点です。これは単にツールが導入されただけでなく、AIを軸とした「学習する組織文化」が根付き始めたことを示しています。
AI活用を成功させる鍵は、ツール導入そのものよりも、チームで学び、成長し続ける文化をいかに育むかにある、という重要な示唆が得られました。
登壇者:株式会社ラクス 北嶋 初音
「AIを開発プロセスにどう組み込むか?」この問いに対し、人とAIがそれぞれの得意な領域で力を発揮する、新しいワークフローが紹介されました。
新規プロダクトのPoC(概念実証)開発という、スピードが命のプロジェクトで、Miroのワイヤーフレームだけを元に「動くデモアプリ」を迅速に構築する必要がありました。そこで編み出されたのが、人とAIの役割を明確に分担した開発フローです。
人とAIの役割分担
- 【人】お手本の実装: 最初の1画面はあえて人が手動で実装。コーディング規約や設計パターンといった「お手本」をAIに示す。
- 【AI】土台の実装: 「お手本」コードとワイヤーフレームを元に、AIが2画面目以降の土台を高速で生成(完成度30〜60%)。
- 【人とAI】壁打ち修正: 人がAIに具体的な修正指示を出し、対話しながら完成度を80%まで高める。
- 【人】仕上げとレビュー: 細かなUI調整や動的な挙動の実装、最終的なコードレビューは人が担当。
このアプローチにより、体感で30〜40%の工数削減を実現しただけでなく、流動的な仕様変更にもスピーディに対応できるようになったとのこと。
結論は明快です。「0→1」の初期設計と「80→100」の最終品質担保は人が担い、その間の定型的な実装作業はAIに任せる。この賢い棲み分けこそが、AIドリブン開発を成功させる核心と言えるでしょう。
登壇者:株式会社ラクス 大口 詩織
大規模で長く運用されているシステムにおいて、品質を保証するためのリグレッションテストは、時に開発のボトルネックとなります。このセッションでは、膨大なテストケースの選定作業を、AIを用いて自動化した非常に高度な事例が紹介されました。
課題は、毎回手動で行っていたテストケースの選定作業の負担が大きいこと。そこで、「バグが起きやすい機能をデータから特定し、テストを優先順位付けする」という目標を立て、過去2年分・約1000件のGitコミットログの分析に挑みました。
この膨大かつ複雑な分析は、人手では現実的ではありません。そこで考案されたのが、AIによる独創的なアーキテクチャです。
“Manager-Worker”モデルによる自律処理
- AIツールの使い分け: 方針決定の壁打ちにはChatGPT、具体的な分析作業にはClaude Codeと、役割に応じてAIを使い分け。
- 自律的な並列処理: 1体の「Manager」役AIが、複数の「Worker」役AIに分析タスクを割り振る構成を構築。これにより、AIチームが自律的に並列で作業を進める仕組みを実現。
この取り組みにより、人間が介在せずとも処理が進む「手離れ」を高いレベルで実現するという大きな成果を収めました。一方で、Workerが作業を停止してしまうなど、自律エージェントならではの新たな課題も見えてきたとのこと。ビジネスの根幹にある泥臭い課題に、革新的なアプローチで挑んだ好例です。
登壇者:株式会社ラクス 石田 浩章
長年開発されてきた複雑なシステムにAIを導入しようとすると、「過去の設計経緯が不明」「仕様書が整理されていない」「コード量が多すぎてAIが扱えない」といった壁に直面します 。なぜなら、既存の開発はチームに蓄積された「暗黙知(コンテキスト)」に支えられているからです。
このセッションでは、AIの真価を引き出す鍵となる「コンテキストエンジニアリング」というアプローチが紹介されました 。これは、AIが人間の意図を正確に理解するために必要な「情報(コンテキスト)」を、いかに設計し、構造化するかという技術です 。
マネージャーとして取り組むべき3つの解決策
- ① コンテキストストリーム設計: ビジネスサイドも扱いやすいGoogleドキュメントで要求をまとめ、開発側が管理しやすいMarkdown形式でGitHubに連携させるなど、情報の流れを整えます 。
- ② AIによる自動化と支援: ドキュメント形式の変換をAIで自動化したり、専門知識が必要な仕様の整合性をAIにチェックさせたりすることで、属人性を排除します。
- ③ できる限りの情報を残す: なぜその技術を選んだのかという背景を「ADR(Architecture Decision Record)」として記録するなど、未来のチームとAIのために、意図的にコンテキストを残していくことが重要です。
重要なのは、より賢いモデルを待つことではなく、「課題に最適なコンテキストを与えること」 。チーム、関係者、そしてAI自身がより良く開発していける環境を整えることこそ、マネージャーとしてのコンテキストエンジニアリングであると語られました 。
登壇者:paiza株式会社 高村 宏幸 氏
最後のセッションでは、これまでの具体例を俯瞰し、AI活用で真の競争優位性を生むための戦略的な視点が示されました。
高村氏は、AI活用には「光」と「闇」の2つの側面があると語ります。
- 光の側面
- デモ映えする派手な活用法(例:0→1のアイデア創出)
- トレンドの進化が速く、追随しないと競合に劣後する「守り」の一手
- 闇の側面
- 地味で泥臭いが、ビジネスの根幹に関わる課題解決
- 自社特有の巨大なコンテキストが必要で、競合が真似しにくい
- 真の競争優位性を生み出す可能性を秘める
高村氏が強調するのは、「目的はAIを使うことではなく、ビジネスの課題を解決することだ」という原則です。たとえAIで実装が速くなっても、レビューやテストが新たなボトルネックとなり、全体のリリースサイクルが短縮されなければ意味がありません。
私たちは、流行りの「魅せ球(光)」を追いかけるだけでなく、自社の文脈に深く根ざした、競合が模倣困難な「決め球(闇)」を磨き続ける必要がある、という力強いメッセージでセッションは締めくくられました。
今回のイベントを通じて見えてきたのは、AIドリブン開発の成功は、単一のツールや魔法によってもたらされるものではない、という力強い現実でした。成功への道筋は、一つの成熟度モデルとして描くことができます。
まず、個人に依存せず、チームで学び成長する組織的な基盤を築きます。その上で、人とAIの得意領域を見極め、協業させる戦術的な高速化を実践する。さらに、既存システムの複雑さという壁を乗り越えるために、戦略的にコンテキストを設計し、AIに与える。そして、現場の真の痛みを解決するため、AIを自律的なエージェントとして活用し、価値の高い課題に挑む。これら全ての活動を、ビジネスの「本質的な課題解決」へと方向づける戦略的思考が、その羅針盤となるのです。
イベント全体を貫くテーマとして「コンテキスト」の重要性が繰り返し示されました。ラクスとpaiza社が共有したリアルな知見が、皆さまの開発現場をより良くする一助となれば幸いです。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました!