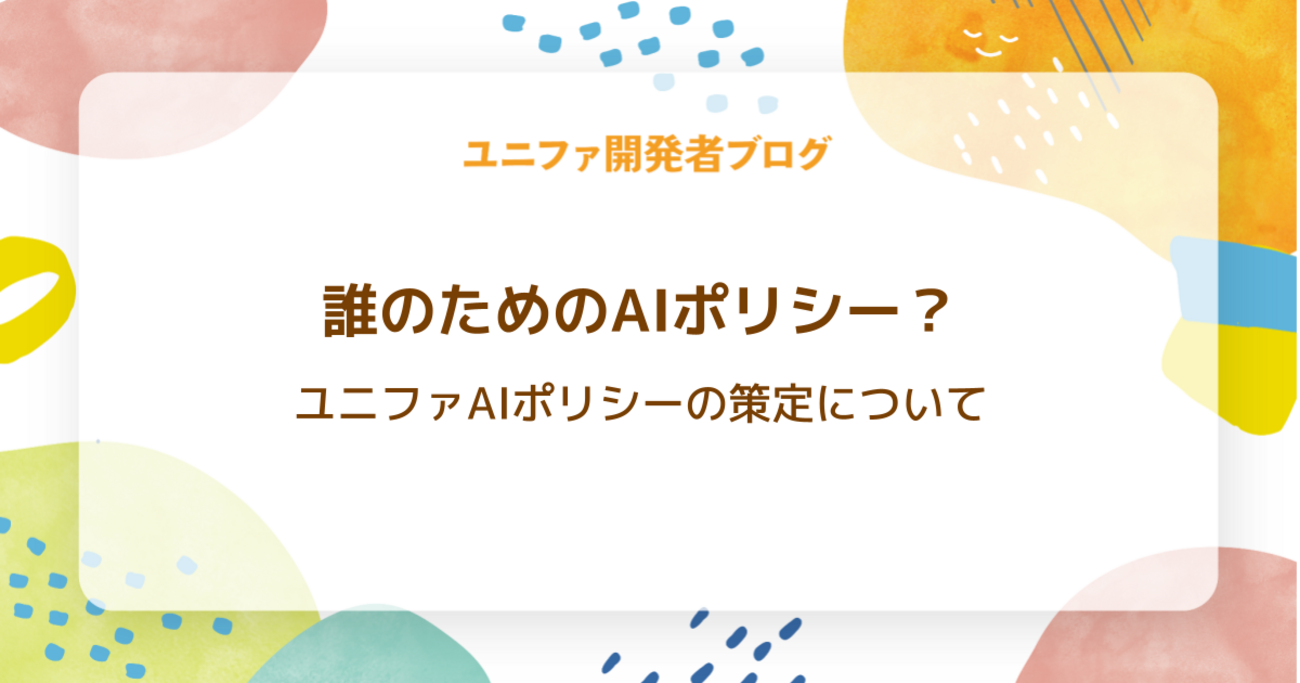こんにちは。ユニファCPOのやまぐち(@hiro93n)です。
最近は保育AIの人として園・施設の先生方にお話する機会が増えており、登壇の引きとなる小ネタで頭を悩ましています。今回はユニファで10/30に制定したAIポリシーをどのような考えで立ち上げたかについてお話をしていきます。
ユニファの運営するルクミーでは保育AIプロダクトを展開しているのですが、これまでAIポリシーが存在していませんでした。
これまでも商談の場などでAIポリシー的なものを求められる場面はあり、その都度、AIに対する方針を一から作成したり、ご説明に伺ったりしていました。ただ、あまり持続可能性がないなとは感じていました。なぜなら全部に自分が呼ばれてしまうからです。
そんな中、PMとして手がけている「すくすくレポート」の公開のめどがついたこともあり、9月上旬から取り組み始めたのがAIポリシーの策定です。
まずは真似ぶところからと、すでに公開されている他社のポリシーを調査することから始めました。ポリシーの必要性がここで定義されているので当然ですが、経済産業省(経産省)のAI事業者ガイドライン(下記リンク先参照)に沿ったものが多く、一定の型が見えてきました。
ただ、ガイドラインに倣ったことを宣言して、ルール化するだけでいいのか?それをあえて宣言して、確かにコミュニケーションはラクになるかもしれないが安易な結論に落ちていないかと思い、今一度これまで自分たちが大事にしていた考えや方針を棚卸してみることにしたのです。
最近セミナーで話すこととして「私たちが保育AIを推し進めるのは、こどもに関わる当事者に関わらず、関わる人がこどものことを知るためのコストを下げたいから」とお伝えしています。

その結果として間接的に業務負荷が軽減されるようなこともあるとは思いますが、メインはこどもにあります。つまりは意図せずこどもに不利益のあるようなAIの使い方は推奨したくなく、むしろ避けるべきと考えています。
こどもの利益を考えないAIによる意思決定や、成立のためにこどもへ過度な負担を強いるAIプロダクトを生み出すことは本意ではない、という視点も自分の中にあり、改めて言語化した上で社内でもAIポリシーの素案として提示しました。
そして最終的に着地したポリシーが下記のリンク先にあるものです。もともとのポリシーを研究開発(R&D)部門や経営チームとも議論し、合意に至りましたが、ちょっとしたビジョンの策定に近い議論であったと感じます。
AIポリシーは、ガバナンスの開示にとどまらず、『誰の、何のために、どのようにAIを扱うのか』という姿勢を示す宣言でもあります。
ポリシーの内容そのものだけでなくAIに関する研究開発の考え方や事業展開、AI倫理などの認識を改めて確認するきっかけとしてもよかったと思っていて、意見が分かれる点は適切に議論し、言うべきところは明確に主張することができました。
私たちが保育AIに取り組みはじめたのは2023年のことで、その頃はまだ多くのことが探り探りで、AIに対する姿勢を言語化することなど考えていませんでした。
2025年になりAIを使うことが一般的になり、さらに深い使い方をする上での安全性、信頼性が求められるフェーズになっています。今回策定したポリシーも1〜2年経つと時代に合わなくなることはあるはずで、定期的に時代と技術に合わせたアップデートが必要です。
保育AIがインフラになっていく上で「AIで実現できるんだから何をやっても良い」というスタンスは許されません。私たちはAIポリシーとともに、今後の保育AIを主体的に切り開いていきたいと思います。
求人コーナー
ユニファの開発チームでのプロダクト開発にご興味を持っていただけましたら、ぜひ募集要項をご覧ください!