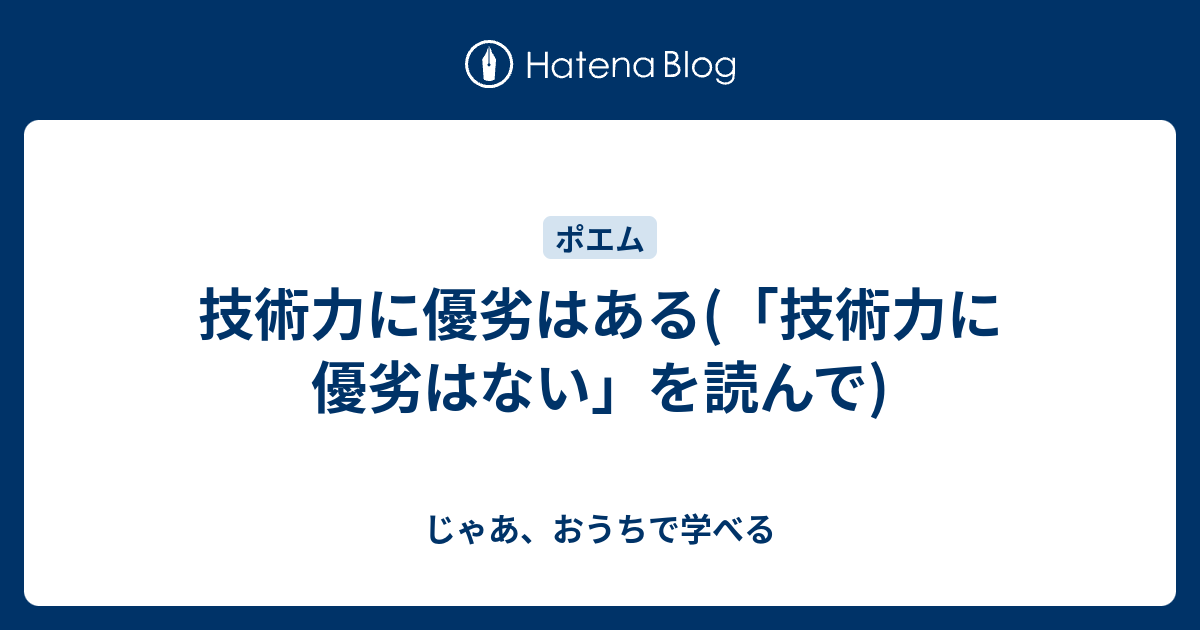はじめに
先日、「技術力に優劣はない(技育などに参加している学生に向けて)」という記事を読みました。技育に参加する学生たちへの励ましのメッセージで、技術との向き合い方の多様性を認め、コミュニケーション力の重要性を説き、相互リスペクトの大切さを訴える、とても温かい内容でした。
この記事は、あの記事の対象読者ではない私が、横から口を出すような形になってしまうことを承知で書いています。 元の記事の主張——技術の感受性には段階があること、ジュニアにはコミュニケーションが大事なこと、べき論に揺さぶられないこと、どの段階にいてもキャリアは作れること——これらは本質的に正しいと思います。
ただ、私はこう思います。それでもなお、技術力という軸においては、やはり優劣が存在し、それが中長期的なキャリアに大きな影響を与えます。
このブログが良ければ読者になったり、nwiizoのXやGithubをフォローしてくれると嬉しいです。では、早速はじめていきましょう。
技術との向き合い方
元の記事では、技術への向き合い方を3段階に分けていました。この分類は本質を捉えていると思います。
- 技術を道具として使う人
- 技術を理解する人
- 技術を創る人
この分類自体はとても良いのですが、私はこれをポケモンの進化のような段階的なものとは捉えていません。むしろ、これらは固定的な段階ではなく、状況や分野によってシームレスに行き来するものだと感じています。
例えば、Reactについては深い理解があり、新しいパターンを生み出せる人でも、機械学習の分野では既存のライブラリを使うだけかもしれません。人は常に3つの状態を往復しています。新しい分野に挑戦すれば「道具として使う」状態に戻りますし、経験を積めば「理解する」状態に移行し、さらに探求すれば「創る」状態に到達します。
それぞれの状態の中には優劣は存在する
ここで重要なのは、これら3つの状態は確かに流動的ですが、それぞれの状態の中には明確に優劣が存在するということです。
「道具として使う」中には優劣があります。 同じ「道具として使う」状態でも、ドキュメントを読んで適切に活用できる人と、エラーが出たらすぐに諦めてしまう人では、生産性に大きな差があります。基本的な概念を理解しながら使っている人と、ほぼブラックボックスとして使っている人では、応用力が全く異なります。そして今、生成AIを効果的に活用できる人とそうでない人では、学習速度に圧倒的な差が生まれています。エラーメッセージをAIに投げて適切な解決策を引き出せる人と、ただコピペして満足する人では、問題解決能力が変わってきます。
「理解する」中には優劣があります。 内部実装を読んで理解している人と、公式ドキュメントレベルの理解に留まっている人では、問題解決能力に差があります。パフォーマンスの特性やエッジケースまで把握している人と、基本的な使い方だけ知っている人では、設計の質が変わってきます。ここでも生成AIの活用法に差が出ます。複雑なコードベースの理解を加速するためにAIを使える人と、単に「これ何してるの?」と聞くだけの人では、深い理解への到達速度が違います。技術的な仮説を立て、AIに検証させながら学びを深められる人は、独学だけの人より効率的に専門性を高められます。
「創る」中には優劣があります。 既存のものを少し改良したレベルと、まったく新しいパラダイムを生み出すレベルでは、技術的なインパクトが桁違いです。自分のプロジェクトで使える小さなライブラリを作る人と、業界全体に影響を与えるOSSを開発する人では、その影響力は比較になりません。そして今、生成AIを創造のパートナーとして使いこなせる人とそうでない人では、アウトプットの質と量に大きな差が生まれています。アイデアの壁打ち相手としてAIを使い、設計の初期段階を加速できる人。実装の定型部分をAIに任せ、本質的な設計に集中できる人。こういった使い方ができる人は、同じ時間でより高度なものを創り出せます。
向き合い方の違いを優劣として捉えがち
しかし、学生や若いソフトウェアエンジニアは、この向き合い方の違いを、ソフトウェアエンジニアとしての優劣として捉えがちだという側面があります。
「自分は道具として使っているだけだから、ダメなエンジニアだ」
「あの人は技術を創っているから、自分よりずっと上だ」
こういった思考に陥りやすいです。それが過度な自己否定につながったり、逆に、ある分野で「創る」状態に到達したことで慢心したりします。
しかし、向き合い方は分野によって変わります。誰もが全ての技術について「創る」状態にいるわけではありません。そして、「道具として使う」状態であることが、必ずしも劣っているわけではありません。
重要なのは、どの状態にいるかではなく、その状態の中でどのレベルにいるか、そして複数の領域でどう組み合わせているかです。
能力ではなく衝動や偏愛
人を「道具として使う」状態から「理解する」状態へ、さらには「創る」状態へと突き動かすものは、おそらくは計画的なキャリアデザインではありません。むしろ、それは衝動や偏愛に近いものだと思います。あるいは、そうした衝動を自然と抱けるような環境に身を置けるかどうかです。
「なぜかこのエラーメッセージが気になる」「この実装がどうなっているのか知りたくて仕方がない」「この技術で何かを作りたいという衝動が止まらない」——こういった、理屈では説明しきれない偏愛が、人を技術の深みへと引き込んでいきます。そして、周囲に技術を深く追求する人たちがいる環境は、そうした衝動を自然と育んでくれます。
それでもなお、市場価値の差は存在する
しかし、この3つの状態の間には、やはり市場価値の差が存在します。そして、どの状態に長く留まっているか、その状態の中でどのレベルにいるかが、中長期的なキャリアに大きな影響を与えます。
「道具として使う」状態に留まり続けることのリスクは、年齢を重ねるほど大きくなります。表面的な理解しかないエンジニアは、年齢を重ねると「代替可能な人材」になっていきます。若手の方が給与が安く、学習意欲も高いです。同じ「道具として使う」状態であれば、企業が選ぶのは若手です。
一方、主要な技術領域で「理解する」状態に到達できれば、市場価値は変わります。そして、いくつかの領域で「創る」状態に到達している人は、さらに大きな影響力を持ちます。さらに、同じ「理解する」状態でも、そのレベルの高さによって市場価値は大きく変わってきます。
この差を「優劣ではない、違いだ」と言えるでしょうか? 市場は明確に評価しています。
ジュニアに技術力は求められていない?
元の記事は「ジュニアに技術力は求められていない」と述べていました。確かに、新卒や入社1〜2年目であれば、それは正しいです。しかし、これを「技術力を磨かなくてもいい理由」にしてはいけません。
年収600万円を超えるには、以下のような能力で「自立レベル」への到達が求められます。
- 設計力/実装力:アーキテクチャ設計、コーディング、技術選定など
- 専門性の深さと広さ:特定領域の深い知識と、周辺技術の幅広い理解
- 推進力・プロジェクト貢献:プロジェクトを前に進める力、スケジュール管理
- 組織貢献:チームビルディング、メンバー育成、採用への貢献
- 事業・顧客貢献:ビジネス価値への理解、顧客課題の解決
- 情報発信・プレゼンス:技術ブログ、登壇、OSS活動など
このレベルに到達するのは、通常は入社3〜5年目だと言われています。つまり、「ジュニアには技術力は求められていない」というのは、せいぜい20代半ばまでの話です。それを過ぎても設計力/実装力や専門性が低いままだと、キャリアは確実に行き詰まります。
コミュニケーション力と技術力は対立しない
元の記事では、技術の勉強をしている人とそうでない人が対比され、後者は「別の有意義なことをしている」と書かれていました。
確かに、ゲームをしたり、友達と飲みに行ったりする時間は人生において大切です。キャリアは短距離走ではなく、中長距離走です。 燃え尽きないことが重要であり、適度な息抜きや趣味の時間は必要です。
しかし、それは「技術を学ばない理由」にはなりません。 むしろ、中長距離だからこそ、地道な積み重ねが最終的に大きな差を生みます。1年、3年、5年と継続的に学び続けることで、技術力は確実に向上します。
なぜなら、優秀なエンジニアは、技術力もコミュニケーション力も両方高いからです。これは対立するものではなく、掛け算で効いてくるものです。
私が見てきた優秀なエンジニアたちは、例外なく以下の特徴を持っていました。
- 設計力/実装力が高い(主要技術について「理解する」以上の状態)
- コミュニケーション力も高い
- ビジネス理解力がある
- 学習意欲が高い
「技術力がないから、コミュニケーション力で勝負する」というのは、戦略ではなく妥協です。本当に市場価値を高めたいなら、先ほど挙げた6つの能力を、バランス良く磨く必要があります。
キャリアの中盤で見えてくる分岐点
20代のうちは、技術力の差はそれほど致命的ではません。コミュニケーション力や調整力でカバーできるし、「これから成長すればいい」という期待値もあります。
しかし、キャリアの中盤になると、市場が求めるレベルは急激に上がります。
- 技術的な意思決定ができること
- チームをリードできること
- アーキテクチャ設計ができること
- 若手を育成できること
これらはすべて、高い技術力を前提としています。 コミュニケーション力だけでは、技術的な意思決定はできません。表面的な理解では、アーキテクチャ設計はできません。自分が技術を深く理解していなければ、若手を育成することもできません。
早期のマインド切り替えと継続的な努力
「追いつけない」ではなく「只々積み上げる」
元の記事には、圧倒的なテックリードを見て「自分が3に行けることはないと実感した」という記述があった。この気持ちはよくわかります。圧倒的な技術力を持つ人を目の当たりにしたとき、「自分には無理だ」と感じる瞬間は、多くのエンジニアが経験することです。
しかし、そのテックリードもまた、努力の積み重ねでそこに到達しているということを忘れてはいけません。彼らは最初から「創る」状態にいたわけではません。膨大な時間をかけて技術を学び、無数のエラーと格闘し、何度も失敗を繰り返し、そして徐々に深い理解を獲得していった。
「あの人は天才だから」と片付けてしまうのは、その人が積み重ねてきた努力を見ないことになります。そして、自分自身の成長の可能性を閉ざすことにもなります。その積み重ねを軽く見てはいけません。
確かに、技術に対する偏愛や衝動の強さは人それぞれです。しかし、それでもなお、努力で到達できる範囲は思っているより広いです。 毎日1時間でもいいです、技術書を読みましょう。個人プロジェクトに取り組みましょう。エラーメッセージと真剣に向き合いましょう。こういった地道な積み重ねが、1年後、3年後、5年後の自分を作ります。
技術力が高いエンジニアは、キャリアの中盤以降も選択肢が広がり続けます。一方、主要技術について表面的な理解に留まっているエンジニアは、選択肢が狭まっていきます。これが、早期に技術力を磨くことの重要性です。
やる気は行動の後からついてくる
「技術を学ばなければ」と頭では理解していても、なかなか実行に移せません。モチベーションが湧かません。やる気が出ません。こういった悩みを抱えている人は多い。
しかし、ここで重要な真実があります。やる気を出すには、やるしかません。
多くの人は「やる気が出たら始めよう」と考える。しかし、これは因果が逆です。やる気は行動の前に現れるものではなく、行動の後からついてくるものです。
心理学の研究でも明らかになっているが、人間の脳は「行動を始めてから」やる気を出すようにできています。作業興奮という現象です。まずは5分だけコードを書いてみる。1ページだけ技術書を読んでみる。すると、脳が活性化し、自然と続けたくなります。
「理想的な環境が整ったら」「十分な時間ができたら」「気分が乗ったら」——こういった条件を待っていても、その日は永遠に来ません。理想的な状態を待つのではなく、不完全なままでも始めることです。
毎日30分でいいです。週末の2時間でいいです。小さく始めて、継続しましょう。それが1ヶ月、3ヶ月、1年と続けば、気づいたときには大きな差になっています。
「やる気が出ないから動けない」のではなく、「動かないからやる気が出ない」のです。だから、やる気を出すには、やるしかありません。 今この瞬間から、小さな一歩を踏み出しましょう。
学生のうちに気づけるなら
私が最も伝えたいのは、早期にマインドを切り替え、只々研鑽を積み重ねることの重要性だ。早く気づけば気づくほど、リカバリーは容易になります。
学生なら今が絶好のタイミングです。時間はたっぷりあります。大学の授業だけでなく、個人プロジェクト、OSS、インターン——自分に合った形で技術と向き合いましょう。
一時の成功も失敗も、長い人生の中では泡のようなものです。 今日のコンテストでの勝利も、明日の挫折も、それ自体は大した意味を持たません。重要なのは、そこから何を学び、次にどう活かすかです。
そして、本当のトップレベルを見に行こう。 自分より優秀な人たちがいる環境に飛び込み、「ボコボコにされる」経験をしましょう。それは屈辱的かもしれないが、それこそが成長のチャンスです。
ただし、一度の挫折で諦めないでほしいです。 圧倒的な実力差を見せつけられても、それは終わりではありません。自分の現在地を知る機会です。そこから、只々積み上げていけばいいです。
社会人になってから気づいても遅くはない
20代であっても、キャリアの中盤であっても、「技術力を磨かなければ」と気づいた時点から始めれば、必ず変わります。ただし、学生時代より難易度は上がります。家庭があるかもしれません。体力も落ちているかもしれません。それでも、今から本気で取り組めば、道は開けます。
業務時間外の勉強を習慣化しましょう。技術書を読みましょう。個人プロジェクトを作りましょう。2〜3年本気で取り組めば、主要技術について表面的な理解から深い理解へと確実に移行できます。そうなれば、市場価値は大きく変わります。
気づいた時点が、あなたにとっての「今」です。過去を悔やむより、今から只々積み上げていきましょう。
キャリア戦略の選択肢
エンジニアとして生きていく上で、大きく分けて2つの戦略があります。
選択肢1: 技術のスペシャリストを目指す
本気で技術を磨き、技術者として高い評価を得られるエンジニアになります。これは楽な道ではません。業務時間外も勉強し、常に新しい技術にキャッチアップし、OSSにコントリビュートし、深夜までコードを書きます。
しかし、その努力は報われる。キャリアの中盤で選択肢が広がり、技術者としての充実感を得られます。市場価値も高く、転職の選択肢も豊富です。
選択肢2: 技術とビジネスのバランス型を目指す
設計力/実装力は一定レベルに抑え、組織貢献や事業・顧客貢献で価値を出す。プロダクトマネージャーやエンジニアリングマネージャーを目指す道です。
これも立派な戦略です。しかし、技術の基礎理解は必須です。 表面的な理解だけで「マネジメントに進む」というのは、逃げに過ぎません。マネージャーやPMになっても、技術を深く理解していなければ、チームから信頼されず、技術的な制約や可能性を踏まえた意思決定もできません。
どちらを選ぶにせよ、技術力に優劣があることを認め、自分の現在地を正確に把握することが、全ての出発点です。 そして、気づいた時点から、只々積み上げていくことが大切です。
一つの物差しで人を測るな
ここまで技術力の重要性を語ってきたが、同時に伝えておきたいことがあります。
学生時代から社会人の初期にかけて、私はカンファレンスやイベントで、相手の技術的な知識を試すような会話をしていました。わざと難しい質問を投げかけて、相手が答えられないのを見て優越感に浸る。今振り返ると、最低です。
当時の私は、技術力の有無だけで人間の優劣を測っていました。学生のギーク層にありがちな行動だが、自分がイキれる相手を見つけて、マウントを取るのは確かに気持ちがいい。でも、それは恥ずべき行為です。
ただし、逆の極端も問題だと思っています。
世の中には「技術力なんてどうでもいい、面白い人間かどうかが全て」という価値観もあります。確かに、人間的な魅力は重要です。でも、それを唯一の評価軸にして「技術バカは使えない」「コミュ力こそ全て」と言い切るのも、結局は別の物差しで人を測っているだけです。
技術力で人を測るのも、コミュ力で人を測るのも、面白さで人を測るのも、本質的には同じ過ちです。
この記事で私は「技術力の優劣を直視せよ」と書いてきた。市場価値という文脈では、技術力の差は厳然として存在します。それを無視してキャリアを語ることはできません。
しかし、それはあくまで市場価値という一つの軸での話です。 技術力が高いからといって人として偉いわけではません。逆に、技術力が低いからといって人として劣っているわけでもません。
イベントで出会った人が、あなたより技術的な知識が少ないように見えても、その人にはその人の文脈があります。学びの途中かもしれません。別の分野のエキスパートかもしれません。技術以外の部分で圧倒的な価値を生み出している人かもしれません。
大切なのは、相手の文脈を読み取って会話できることです。 自分の得意な物差しだけで人を評価し、優越感に浸るのは、いくら専門性が高くても人として未熟です。技術力を磨くことと、人として成熟することは、まったく別の話なのだから。
おわりに
長々と書いてきたが、最後にもう一度、元の記事への敬意を示したい。元の記事は、学生たちを励まし、多様性を尊重し、相互リスペクトを訴える、とても温かい内容でした。その優しさと配慮は、本当に素晴らしいと思います。
私はこの記事で「技術力に優劣はある」と主張してきた。それは市場価値やキャリアという観点では事実です。
しかし同時に、技術力で人間の価値を測ってはいけません。技術力が高いことと、人として成熟していることは別物です。むしろ、技術力があるからこそ、謙虚さとリスペクトを忘れてはいけません。
「優劣はない」という優しい言葉に安住せず、現実を直視してほしいです。そして、今のうちに本気で技術を学んでほしいです。キャリアは中長距離走です。 今なら、まだ間に合います。
ただし、技術を学ぶ過程で、決して人を見下してはいけません。相手の文脈を理解し、リスペクトを持ってコミュニケーションを取りましょう。それができて初めて、優秀なエンジニアと言えるのだと思います。
この記事は、元の記事の筆者や読者を否定する意図はありません。対象読者ではない私が横から口を出すような形になってしまい申し訳ありませんが、学生時代の自分に伝えたかったこと、そして過去の自分を反省する気持ちを込めて書きました。